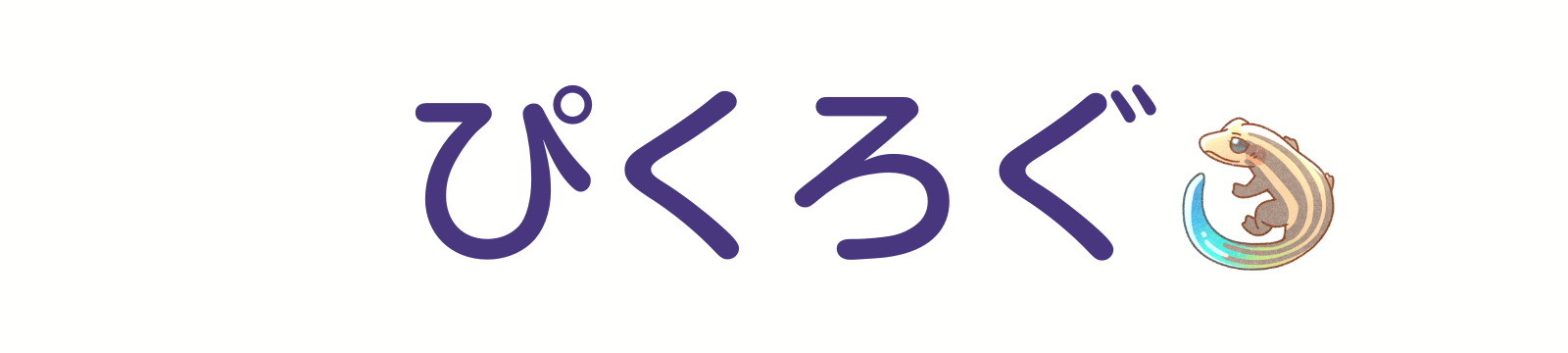夜空に、月とは別の光が満ちる世界を想像したことはあるでしょうか。
それは地上にクリーンなエネルギーを届け続けようと、
人類が宇宙に築いた「第二の太陽」。
太陽発電衛星(SPS: Solar Power Satellite)計画とは、
そんなSFのような未来を本気で目指した、壮大なエネルギープロジェクトです。
天候に左右されず、宇宙から連続的に太陽光を地球へ送る。
では、なぜ今も私たちの空にこの人工の太陽は浮かんでいないのでしょうか。
この記事では、太陽発電衛星という未完のプロジェクトが歩んだ軌跡と、
その技術が照らし出す未来の可能性を、できる限り一次資料に基づいて紐解いていきます。
※注:「24時間365日完全に途切れない」わけではなく、ほぼ連続的な発電が可能というものとのこと。
太陽発電衛星(SPS)計画とは?(概要・背景)
空を見上げるたび、人類はそこに新天地を描いてきました。
太陽発電衛星計画、それは
宇宙空間そのものを地球文明を支えるための巨大なエネルギーインフラに変えようとする野心的な試みです。
いつ・誰が・どこで・何を目指したのか
太陽発電衛星の基本構想が広く知られるようになったのは1968年、
アメリカの宇宙工学者ピーター・グレイザー博士が科学誌「Science」に寄稿した論文からでした。
博士は、地上約36,000kmの静止軌道上に巨大な太陽電池アレイを展開し、
得られた電力をマイクロ波に変換して地上のレクテナに送電するというシステム像を描きました。
これにより、天候や夜間の制約を大幅に回避し、
ほぼ連続的なクリーン電力を確保することを目指したのです。
※用語注:レクテナは「Rectifying Antenna(整流アンテナ)」の略称で、
受信した電磁波を直流電力に変換するアンテナ配列です。
※用語注:静止軌道とは、地球の自転と同じ速さ・同じ向きで回るため、
地上から見ると常に同じ場所の空に「止まって」見える円軌道のことです。
なぜ立ち上がったのか(当時の状況)
この構想が国家レベルで本格検討に進んだのは、
1970年代のエネルギー危機(オイルショック)が直接のきっかけです。
1977〜1980年には、米国エネルギー省(DOE)とNASAが共同で「SPS 概念開発・評価(CDEP)」を実施。
出力約5GWの発電衛星、約5km×10kmの太陽電池アレイ、
直径約10kmの地上レクテナからなる「基準モデル(リファレンス・システム)」を定義し、
技術・安全・コストなどを総合的に評価しました。
太陽発電衛星計画の技術と仕組み
それは宇宙空間に巨大な送電網を築くような、壮大な挑戦でした。
地上とは全く異なる環境で前例のない規模のシステムを機能させるためには、
いくつもの革新的な技術を組み合わせる必要がありました。
中核となる技術要素
太陽発電衛星システムは、主に3つの核心技術で構成されます。
- 宇宙でkm²級の面積を持つ太陽電池アレイと送電アンテナを建設・維持する宇宙巨大構造物技術
- 直流電力をマイクロ波(またはレーザー)に高効率で変換する電力変換・送電技術
- 宇宙から地上レクテナへビームを正確に届ける高精度ビーム指向・位相制御技術
これらが同期して初めて宇宙からのエネルギー供給が成立します。
※用語注:マイクロ波は周波数約300MHz〜300GHzの電磁波帯。
SPSでは2.45GHzや5.8GHz帯の検討が古典的に多く、
レクテナのRF-DC変換効率は実験室レベルで80〜90%が報告されています。
どのように実現しようとしたか
想定されている流れは、次のとおりでした。
- 複数回のロケットで部材を低軌道(LEO)に運び、そこでロボット等で巨大構造物として組み立てる。
- 完成後に静止軌道(GEO)へ移し替え、ほぼ途切れない太陽光を受けて発電。
- 得た電力をマイクロ波へ変換し、地上の数km規模のレクテナ(受電用アンテナ)に照射。
- そこで直流に整流して取り出し、変換設備を通して送電網に接続。
計画が要求した技術水準
- 衛星(アレイ)サイズ: 約5km × 10km級(DOE/NASA リファレンス)。
- 出力規模: 系統連系で約5GW級(原子力・大規模火力に相当)。
- 総重量: 数万トン級(設計による幅あり)。
- 総合効率: 宇宙DC→RF→地上DCのエンドツーエンドで概ね50%超が望ましい目標(要素効率の積に依存)。
- ビーム制御: 約36,000km先から地上数kmスケールのレクテナに継続的に指向・トラッキング。
太陽発電衛星はなぜ未完に終わったのか
偉大な夢ほど、その前に立ちはだかる壁もまた高くなります。
太陽発電衛星は技術的なハードルだけでなく、
経済的、社会的な課題という名の厚い雲に覆われ、
実現への道のりは閉ざされていきました。
技術的・安全上の課題
数万トン規模の資材を宇宙へ運び、軌道上で巨大構造物を建造・維持するという技術は、
当時はまだまだ未成熟でした。
強力なマイクロ波ビームの生体・環境影響や航空機・衛星機器への電磁干渉評価、
宇宙デブリとの衝突回避・損傷許容設計など、実証に基づく安全性担保も課題でした。
政治的・経済的・社会的要因
最大の障壁は巨額なコストでした。
DOE/NASAは、建造・輸送・運用の前提が、
当時の技術水準では極めて高コストになることを示し、
1981年には米議会のOTA(議会技術評価局)や全米研究評議会(NRC)が
技術成熟度・コスト・制度面の懸念を指摘しました。
これらの評価や財政環境も重なり、米国の国家プロジェクトは1980年代初頭に収束しました。
もしも太陽発電衛星が実現していたら
もしあの時、空に人工の太陽が昇っていたなら?
私たちの文明はどんな光景を見ていたでしょうか。
その光は、単に夜を照らすだけでなく、社会のあり方そのものを変えていたかもしれません。
当時描かれていた未来像
砂漠や洋上に大規模なレクテナ群を整備し、地域間の電力を融通できる基幹電源として使う。
そんな将来像が示されていました。
しかしながら、
資源の偏在からの脱却、化石燃料依存の低減、広域での安定供給への期待は大きい一方で、
環境影響や土地利用、電波管理、国際協調(周波数割り当て・安全基準)
といった課題が並行して存在することも、当時の評価書は明確に指摘しています。
現代からの展望と課題
近年は、打上げコストの低下や高効率太陽電池・パワーエレクトロニクスの進歩、
フェーズドアレイの高精度化などを背景に、宇宙太陽光発電の研究が再び活発化しています。
日本では2015年にJAXA/日本スペースシステムが1.8kWを約55m伝送する地上実験、
三菱重工が10kWを約500m伝送する実証を報告しました。
2023年にはカリフォルニア工科大学(Caltech)が、
小型実証機SSPD-1で軌道上無線送電と地上での受信検出を発表し、
2024年に初期ミッションのレビューを公開しました。
中国や欧州でも、大学や研究機関を中心にフルリンク地上検証や技術ロードマップが相次いでいます。
一方で、宇宙デブリの増加、軌道上組立の自動化・冗長化、
国際的な電波規制・安全基準・責任分担など、新旧の課題はなお重要です。
年表
- 1968年:ピーター・グレイザーが『Science』にSPS構想を公表。
- 1977–1980年:米DOE/NASAがSPS概念開発・評価(CDEP)を実施。
5GW級、約5×10kmの太陽電池アレイ、直径約10kmの地上レクテナを含むリファレンス・システムを提示。 - 1981年:米議会OTAが『Solar Power Satellites』評価報告、
NRCが『Electric Power from Orbit』を刊行(技術・経済性・制度面の課題を指摘)。 - 1993年:京都大学・ISY-METSロケット実験(マイクロ波送電の要素検証)。
- 2009年:日本で「宇宙基本計画」を策定(宇宙太陽光発電の研究継続方針を明示)。
- 2015年:JAXA/日本スペースシステムが約55mで1.8kWの無線送電地上実証。
三菱重工が約500mで10kWの送電実証を発表。 - 2023年:Caltechの小型実証機SSPD-1が軌道上送電と地上での受信検出を発表(MAPLE実験)。
- 2024年:Caltechが初期ミッションの成果と教訓を公表(SSPP)。
用語解説
- SPS (Solar Power Satellite)
-
軌道上で発電し、無線で地上に送電する人工衛星。つまり太陽発電衛星。
SSPS(Space Solar Power Systems)とも。 - マイクロ波(Microwave)
-
周波数約300MHz〜300GHzの電磁波。
SPSでは2.45GHz/5.8GHz帯が検討対象。 - レクテナ(Rectenna)
-
受信電波を直流に整流するアンテナ配列。要素実験では80〜90%級のRF-DC効率報告あり。
FAQ(よくある疑問)
- 太陽発電衛星計画はいつ始まった?
-
構想の公表は1968年(ピーター・グレイザー)。
国家レベルの本格評価は米DOE/NASAの1977–1980年CDEP。
日本では1990年代以降、大学・JAXA等で基礎〜要素実証が継続しています。 - なぜ実用化されていないの?
-
当時の輸送・建造コストが桁違いに高く、技術成熟度(軌道上組立・ビーム制御・安全評価)の不足、制度面(周波数割当・国際ルール)も未整備でした。現在はコスト低下と技術進展で機運が再燃していますが、実規模の軌道実証と国際的な安全基準が鍵です。
- 現在も研究は続いている?
-
はい。
日本(JAXA/産学連携)、米国(Caltech/NASA関連研究)、
欧州(ESA内の将来調査)、中国(大学・研究機関のフルリンク地上検証)などで継続中です。近年の軌道小型実証は、まず要素技術が動くかを確かめた段階にとどまっています。
大出力で長期に安定運用できるかの実証は、これからです。 - 宇宙太陽発電でどれくらいのエネルギーが実用可能電力になる?
-
1970年代のDOE/NASAの基準案では、
静止軌道にある1基の衛星が約5GWを地上レクテナへ送る想定(太陽電池アレイは約5km×10km)でした。OTA(米議会技術評価局)は、この前提で容量係数を約90%と見積もっています。
※容量係数=「最大出力でフル稼働した場合に比べ、実際にどれだけ発電できるか」を示す指標。静止軌道は日照ロスが少ないため高くなります。
総合効率は、
衛星の直流電力をRF(マイクロ波)へ変換→大気中を伝搬
→地上で整流して直流に戻す→系統に接続、
という各段階の効率を掛け合わせた値になります。
目標値はおおむね50%以上とされています。※用語注:総合効率とは、システム全体で見た「入口の電力が出口でどれだけ有効電力として取り出せたか」の割合のことです。
宇宙太陽発電(SPS)では、衛星で作った直流(DC)が地上の送電網に載るまでにいくつもの段階を通るため、
各段階の効率を掛け合わせた値になります。 - 発電した電力はどうやって地球に送る?(マイクロ波型・レーザー型の違い)
-
マイクロ波型(現在の主流案)
- 衛星の電力を2.45GHz または 5.8GHzのマイクロ波に変換。
- 地上のレクテナ(受電用アンテナ)で受けて直流に整流し、変換設備を通して送電網に接続。
- 地上実験の実績:1.8kW→約55m(JAXA)、10kW→約500m(三菱重工)。
レーザー型
- 衛星の電力をレーザー光にして送る方式。
- ただし霧・雲・乱流など大気の影響で減衰が大きい。
- 2025年の屋外試験では、1kW照射→1km先で152W受電が報告されています。
※用語注:
- マイクロ波型:電波。雲や雨に強く、広いレクテナで受電→大電力・常時送電向け。
- レーザー型:光。霧や雲に弱く、厳密な指向が必要→小電力・ポイント送電向け。
- 棲み分け:全天候・長距離はマイクロ波。精密・小規模はレーザー。
- 天候や昼夜の影響はある?
-
静止軌道では春分・秋分の前後に日周食が発生し、
最長1日あたり約72分の発電途絶が想定されます(季節限定)。それ以外は天候の影響を受けないのが地上太陽光との大きな違いです。
- 衛星の管理・運営はどの国、組織がおこなうのか?
-
国際法上、宇宙活動は国家の権限と監督の下に置かれ(宇宙条約)、
周波数・軌道はITUの国際調整・登録を通じて管理されます。実運用主体は国家機関または国家の許認可を受けた事業者となるのが原則です。
- 宇宙太陽発電の研究に取り組んでいる国はどれくらいあるか?
-
2024年のNASAのSBSP報告書は、日本(JAXA)、欧州(ESAのSOLARIS)、
米国の大学・研究機関、中国の複数機関など、世界各地の動向をまとめて紹介しています。また、ESAは2023年に、2030年ごろまでの段階的な実証計画を示す資料を公開しました。
- 他の発電(地上太陽光・火力など)と比べてコストは?
-
結論から言えば、まだ確定していません。
- 1980–81年の評価(OTA/NRC):当時の打上げ・建設費を前提に採算は厳しいと判断。
- 近年の再評価(NASA 2024/ESA SOLARIS):
ロケット費の大幅低下や技術進展で可能性は広がったものの、
軌道上組立・運用寿命・保守などの前提に不確実性が大きく、
系統規模での実コストはまだ見積もれないという立場。
- 宇宙太陽発電(SPS)への依存度は高くなるのか?地上だけでもまかなえるのでは?
-
SPSに「高依存」する設計は想定されていません。
SPSの狙いは、夜間・天候の平滑化や資源偏在の緩和などの補完的価値であり、
連系・電波規制・保守などの課題と費用対効果を秤にかけて段階的に判断します。OTA(米議会技術評価局)は、SPSは基幹電源の一候補に過ぎず、
地上の再エネ・原子力・送電強化・蓄電等との相対比較と政策判断が不可欠と述べています。現在の公的レビューも、SPSを多様な電源ポートフォリオの一部として検討。
地域条件や系統要件次第で、地上電源だけで賄うシナリオも成立し得ます。
まとめ
- 結論: 宇宙で発電し、ビームで地上へ送るSPSは基幹電源になり得る。
ただし実規模の軌道実証と国際ルール整備が前提。 - 根拠:DOE/NASAの5GW級リファレンス、JAXA・三菱重工の地上無線送電実証、
Caltechの軌道実証など、段階的な成果が積み上がっている。 - 未完理由: 打上げ・建造コスト、技術成熟度、安全評価・制度整備の遅れ。
- 未来インパクト: 実現すれば気象・昼夜に左右されにくい安定電源としてエネルギー転換を後押し。
ただしデブリ対策・電波管理・環境影響の透明性と社会的合意が不可欠。
太陽発電衛星という壮大なプロジェクトは、
技術的・経済的な壁に阻まれて「未完」のままですが、
要素技術の節目は確実に進んでいます。
夜空に新たな光が灯る日は、科学的検証と国際協調がそろった日である、とも言えるかもしれませんね。
参考資料・出典(一次情報・公的資料)
- 創始・総覧
- Glaser, P. E. (1968). Power from the Sun: Its Future. Science, 162(3856), 857–861.(SPSの基本構想)
- DOE/NASA(米国・1977–1980)
- U.S. DOE / NASA. Satellite Power System: Concept Development and Evaluation Program, Reference System Report(1978/1979)。
- U.S. DOE / NASA. Program Assessment Report: Statement of Findings(1980)。
- NASA NTRS各巻(例:Rectenna/システム検討、5GW・10km級レクテナ等)。
- 米議会・学術評価(1981)
- U.S. Congress, Office of Technology Assessment (OTA). Solar Power Satellites(1981)。
- National Research Council (NRC). Electric Power from Orbit: A Critique of a Satellite Power System(1981)。
- 日本の研究開発
- JAXA「Ground demonstration testing of microwave wireless power transmission」(2015年実験概要)。
- 京都大学RISH「Solar Power Station/Satellite(SPS)」およびISY‑METS関連資料。
- Mitsubishi Heavy Industries(2015年プレスリリース):10kWを約500m伝送する地上実証。
- 近年の軌道実証
- Caltech Space Solar Power Project(SSPD‑1 / MAPLE):2023年「軌道上送電と地上検出」発表、2024年「ミッション成果」公表。
- 効率・技術レビュー
- URSI White Paper on SPS Systems(総合効率目標・安全論点)。
- W. C. Brownほか、レクテナ効率に関するNASA/IEEE資料。