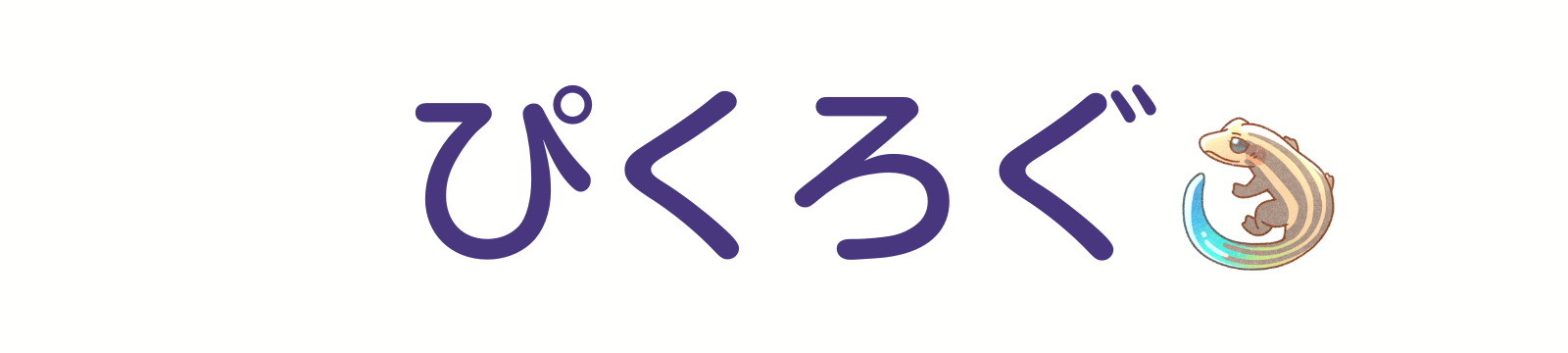もし、空を見上げるだけで、どこにいてもインターネットに接続できたら?
2013年。
Googleは、世界中のインターネット未接続地域に、
空から接続を届けるという構想を公式発表しました。
それが「Loon計画(Project Loon)」、通称「Google 気球」プロジェクトです。
成層圏に多数の気球を浮かべ、それらを「空飛ぶ基地局」として機能させる。
この一見突飛なアイデアは、世界の情報格差を根本から揺さぶりうる試みでした。
しかし、約9年にわたる挑戦の末、プロジェクトは2021年に終了することとなりました。
この記事は、「人類未完のプロジェクト事典」の一章として、Loon計画が何を目指し、
どのような技術で実現しようとし、
そしてなぜ未完に終わったのかを、一次情報に基づいて整理していきます。
Loon計画とは?
空に浮かぶ気球が電波を届ける。
それはSFではなく、Google(後のAlphabet)が本気で追いかけた未来像でした。
いつ・誰が・どこで・何を目指したのか
Loon計画は、インターネット接続が困難な地域に、
成層圏から無線インターネットを提供することを目指したプロジェクトです。
構想はGoogle X(現:X, the moonshot factory)で2011年頃から進められ、
2013年6月のニュージーランド・カンタベリーでの実証実験とともに
「Project Loon」として公式発表されました。
その後、LoonはAlphabet傘下で開発が続けられ、
2018年には独立企業 Loon LLC として位置づけられます。
目標は、従来の地上インフラ(光ファイバーや基地局)の整備が難しい山岳地帯、離島、農村部、
さらに災害でインフラが破壊された地域に対し、成層圏の気球ネットワークを通じて、
既存の携帯端末で利用可能な4G-LTE相当の通信を提供することでした。
※用語注
成層圏(Stratosphere):地上からおよそ10〜50km付近までの層を指す大気の区分。
旅客機が飛ぶ高度(約10〜12km)の少し上から始まる。Loonの気球が飛行したのは主に約18〜20kmの高さ。
なぜ立ち上がったのか?
2010年代初頭時点、Googleは以下のように公式ブログで述べました。
(2013年6月14日付「Introducing Project Loon」)
「地球上の約3分の2の人々にとって、速く手頃なインターネットは依然として手に入らない」と。
そして実際、この「同じ地球上」でありながら、
地形、コスト、政治・社会インフラなどの要因により、
「デジタルデバイド(情報格差)」は深刻でした。
Loon計画は、この問題を解決するために、
「地上ではなく空からネットを届ける」という方法に挑戦したプロジェクトでした。
たくさんの高価な基地局やケーブルを作る代わりに、
高い空を飛ぶ気球を使って広い範囲をカバーし、
通信にかかるコストを下げようとしたのです。
Loon計画の技術と仕組み
飛行高度はおよそ18〜20km前後。
多くの航空機の飛行高度より上に位置する成層圏が、Loonの「空中基地局」のステージでした。
中核となる技術要素
Loon計画は、主に次の3つの技術要素を組み合わせたシステムでした。
1. 高高度気球(High-Altitude Balloon)
この気球はポリエチレンという素材で作られた「スーパー・プレッシャー気球」で、
ふくらんだ状態ではテニスコートくらいの大きさになります。
中には空気の量を変えられる「バロネット」という仕組みがあり、それを使って高さを調整します。
気球の下には、太陽光パネルやバッテリー、通信機器、
そして向きや位置をコントロールするための装置が取り付けられていました。
2. メッシュネットワーク&光無線通信
地上にあるゲートウェイ局から信号を受け取った気球は、
中継役として地上にLTE電波を送りつつ、他の気球ともつながってネットワークを作ります。
ふつうの無線に加えて、実験では気球同士のレーザー通信も使い、
1基あたり約100km、複数の気球をつなげて約1,000kmもの距離までデータを飛ばすことに成功しました。
3. AIによる航行アルゴリズム
気球は横に動くエンジンを持っていないので、自分で好きな方向に飛ぶことはできません。
その代わり、高さを上げ下げして「向きと速さがちがう風」が吹いている高さを選び、
流される方向をコントロールします。
Loonのチームは、成層圏の風のデータと機械学習を使って気球の高さを自動で調整し、
狙ったエリアの近くに長くとどまれるようにする仕組みを作りました。
※用語注
メッシュネットワーク:複数の機器(ノード)が互いに接続し合い、網目状に通信経路を形成するネットワーク。
一部の経路が切れても、別の経路で通信を継続できる強靭性があります。
どのように実現しようとしたか
Loonの仕組みをざっくり言ってみると……
まず、提携している現地の通信会社が持つ「ゲートウェイ局」から、
空に浮かぶ気球へインターネットの信号を送ります。
気球はそれを受け取り、中継基地として、
自分の真下を中心に半径数十kmほどの範囲に4G-LTEの電波を届けます。
利用者は特別な機器を用意する必要はなく、
その地域の電波に対応した普通のスマートフォンで接続できます。
この計画の重要なポイントは、気球をただ風に流されるままにするのではなく、
AIで気球の動きを管理し、必要なエリアに十分な数の気球を集めて、
安定したサービスを保とうとしたところにあります。
Loon計画の主な仕様・記録
- 飛行高度: 約18〜20km前後(成層圏)
- 気球の材質: ポリエチレン製スーパー・プレッシャー気球
- サイズ: 満膨張時はテニスコート程度
- 搭載機器: 太陽電池パネル、バッテリー、LTE基地局相当の無線装置、位置・高度制御システム
- サービス: 地上の携帯事業者ネットワークと連携した4G-LTE接続
(Kenyaなどの実証で音声通話・動画視聴が確認) - 連続飛行記録: 単一気球で312日間の成層圏飛行を達成
(2020年に記録、公的ブログ・技術資料等で報告) - 気球間通信実証: 自由空間光通信により約100kmのリンク、
および7基で約1,000kmのデータ中継を実現
Loon計画はなぜ未完に終わったのか
壮大な構想は、多くの技術成果を生み出しながらも、
技術・安全・規制・ビジネスモデルという現実の多重の壁にぶつかりました。
技術的・安全上の課題
開発の初期では「どれだけ長く飛ばせるか」が大きな問題でした。
数日〜数週間で降りてきてしまう気球も多く、そのたびに対応や回収が必要になり、
コストも手間も大きくなっていました。
改良を重ねた結果、数百日飛び続けられる気球も実現しましたが、
それでもいつかは必ず寿命が来るため、計画的に降下させて安全に回収しなければなりません。
位置のコントロールについても、AIを使った制御によって
「狙った地域の上空にとどまりやすくする」ことはかなり改善されましたが、
静止衛星のように、ずっと同じ一点に固定しておけるわけではありません。
そのため、安定したサービスを提供するには、常に複数の気球を動かし続ける必要がありました。
さらに、多くの気球を成層圏で飛ばすには、
航空管制、安全保障、落下時のリスクなどについて、
各国と細かく調整する必要があります。
Loonは各国当局と協力して運用していましたが、
世界中で常時サービスを行うための仕組みを整えるのは、とてもハードルが高い状況でした。
政治的・経済的・社会的要因
決定打となったのは経済性です。
2021年1月、X(旧Google X)は
「Loon’s final flight」「Saying goodbye to Loon」などの公式記事にて、
「持続可能なビジネスモデルを構築できなかった」ことをプロジェクト終了の理由として明言しています。
事実、気球を作る費用やその気球を飛ばし続ける費用、
落とさず管理する費用、寿命が来たら回収する費用。
さらに、国境や領空、電波のルールに合わせるための手続きや調整にもお金と時間がかかります。
一方で、地上の通信インフラはどんどん安く高性能になり、
低軌道衛星のサービス(衛星コンステレーション)も増えてきました。
その結果、「Loonを選ぶ方が安くて儲かる」とはっきり示すことができず、
ビジネスとして続けるのが難しいと判断された、という見方で公式発表や専門メディアの分析も一致しています。
さらに、気球が国境を越えて移動する特性上、
各国の航空法・電波法・安全保障上の懸念への対応が必須であり、
世界規模での展開には大きな制度的ハードルが立ちはだかっていました。
※用語注
衛星コンステレーション:複数の人工衛星を協調運用し、地球全体や特定地域を連続的にカバーするシステム。
近年の低軌道衛星ネットワーク(例:Starlink等)が代表例です。
Loop計画がもし実現していたら
もしLoon計画が十分な規模で商業的に成立していたら、
「どこでもつながる」という感覚は今日とは違う常識になっていたかもしれません。
当時描かれていた未来像
Loonが想定していたのは、地上インフラが届かない「ラストワンマイル」に対し、
比較的短期間で展開可能な上空ネットワークを提供することでした。
山岳地帯の集落、広大な農村、大洋上の島しょ部などでも、
都市部と同等の情報アクセスを可能にするという未来像です。
また、Loonは災害時インフラとしての期待も実証しました。
2017年のペルー洪水やハリケーン「マリア」後のプエルトリコでは、
各国政府・通信事業者との連携により、被災地で数十万規模のユーザーに暫定的な接続手段を提供したと、
Xおよび提携企業の公式発表で報告されています。
現代からの展望と課題
Loon計画は商業的には終了しましたが、その技術遺産は継承されています。
Loonは成層圏プラットフォーム(HAPS:High-Altitude Platform Station)の実用可能性を世界的に示した代表例のひとつであり、その経験はHAPS Allianceなどの産業連携にも反映されました。
特に、Loonで培われた自由空間光通信技術は「Project Taara」に引き継がれ、
コンゴ川を跨ぐ高速リンクなど、地上での実運用に活用されています。
2025年にはTaaraが独立企業化され、
Loon由来の技術が「レーザーによる中継インフラ」として展開され続けていることが報じられています。
また、ソフトバンクのHAPSMobileなど他社によるHAPS開発や、
低軌道衛星との組み合わせも進行中であり、
「空からのインターネット」はLoon終了後も形を変えつつ追求されています。
年表
| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 2011年頃 | Google X内で高高度気球による通信プロジェクト構想 (コードネーム:Daedalusなど) |
| 2013年6月 | Project Loonとして公式発表。 ニュージーランド・カンタベリーで約30基の気球を用いた実証実験。 |
| 2014年 | ブラジルなどでLTE通信実験を実施。 |
| 2015年 | Google再編によりAlphabet発足。LoonはX内プロジェクトとして継続。 |
| 2016年 | AI航行アルゴリズムが進展し、特定地域上空での滞在性能が向上 (公式ブログで報告)。 |
| 2017年 | ペルー洪水・ハリケーン「マリア」被災地(プエルトリコ)で緊急通信支援を実施。 |
| 2018年7月 | LoonがAlphabet内で独立事業(Loon LLC)として位置づけられたことが発表される。 |
| 2018〜2019年 | 長期飛行や気球間光通信の実証を継続。 約200日規模の飛行や長距離中継を達成。 |
| 2020年7月 | ケニアでTelkom Kenyaと提携し、世界初の商用サービスを開始。 約5万平方kmをカバーする運用が報告される。 |
| 2020年 | 単一気球による312日連続飛行の記録が公表される(技術資料・報道)。 |
| 2021年1月 | Loon計画の終了が公式発表。 理由は「持続可能なビジネスモデルの構築が困難」であると説明。 |
| 2021年以降 | 光無線通信技術がProject Taaraなどへ引き継がれ、 HAPS関連特許の一部はソフトバンク等に譲渡。 |
用語解説
- 成層圏(Stratosphere)
-
地球大気の層の一つで、対流圏の上(おおよそ高度10〜50km)に位置します。
Loonの気球はこの下層部(約18〜20km)を飛行し、
雲や多くの天候現象の上に位置することで、
比較的安定した環境で通信サービスを提供しようとしました。 - HAPS(High-Altitude Platform Station)
-
「高高度プラットフォーム局」の略称。
成層圏に気球・無人機・飛行船などを滞空させ、
広域に通信・観測サービスを提供する仕組みの総称です。Loonは気球型HAPSの代表的な大規模実証例と位置づけられます。
FAQ
Loon計画(Google 気球)はいつ始まったのですか?
高高度気球による通信実験は2011年頃からGoogle X内部で進められていました。
「Project Loon」として一般向けに発表されたのは2013年6月です。
このときニュージーランドでの大規模実証が同時に行われました。
なぜ中止されたのですか?
2021年1月、AlphabetはLoonの終了を発表しました。
その主な理由としては、「商業的に持続可能なビジネスモデルを構築できなかった」ことがあります。
技術的には長期飛行や災害時活用、商用提供など多くの成果があったものの、
コスト構造や規制面を踏まえると、事業として成り立たせることが難しいと判断されたためです。
現在も研究は続いているのですか?
Loon LLCとしての気球インターネット事業は終了しています。
一方で、Loonで培われた自由空間光通信などの技術は
Project TaaraやHAPS関連企業に引き継がれており、
「空や光を使ったインフラ拡張」という発想自体は各社で継続して探求されています。
まとめ
- 結論: Loon計画は、成層圏の高高度気球を「空飛ぶ基地局」として活用し、
未接続地域や災害被災地にインターネットを届けようとしたAlphabetのムーンショットでした。 - 技術: スーパー・プレッシャー気球、AI航行アルゴリズム、LTE基地局、
気球間光通信などを組み合わせ、
既存スマホで利用可能な4G-LTEサービスを空から提供することを目指しました。 - 未完理由: 技術的成果は多かったものの、気球運用コスト、規制調整、
競合技術との比較を含めた採算性の確立が困難であり、2021年にプロジェクトは終了しました。 - 遺産: 災害時接続の実証、HAPS分野の知見、自由空間光通信技術(Project Taara経由)など、
Loonで得られた技術と経験はその後の空・宇宙系インフラに確実に引き継がれています。
Loon計画は「地球上のすべての人をつなぐ」というビジョンに真正面から挑んだ社会実験でした。
その結末は華々しい成功ではなく、厳しい経済合理性と制度的制約の前での撤退でしたが、
その試行錯誤は、HAPSや衛星コンステレーション、
光無線技術など次世代インフラの設計図の一部として生き続けています。
もしLoonがコストと制度の壁を超えられていたなら、
今日私たちが空を見上げるとき、そこには気球が浮かんでいたかもしれませんね。
参考資料・出典(一次情報・公的資料中心)
1. プロジェクト公式発表・終了報告
- Google (2013). Introducing Project Loon: Balloon-powered Internet access. Google Official Blog. https://blog.google/alphabet/introducing-project-loon/
- Astro Teller (2018). Graduation Day: Loon and Wing take flight. X, the moonshot factory. https://blog.x.company/graduation-day-loon-and-wing-take-flight-e23a42620131
- Astro Teller (2021). Loon’s final flight. X, the moonshot factory. https://blog.x.company/loons-final-flight-e9d699123a96
- Alastair Westgarth (2021). Saying goodbye to Loon. X, the moonshot factory. https://blog.x.company/loon-draft-c3fcebc11f3f
2. 技術的成果・実証実験・災害対応
- X (Project Loon). Loon project overview. https://x.company/projects/loon/
- Salvatore Candido (2018). 1 connection, 7 balloons, 1,000 kilometers. X, the moonshot factory. https://blog.x.company/1-connection-7-balloons-1-000-kilometers-74da60b9e283
- X (2017). What it’s like to set up balloon-powered internet during a flood. (ペルー洪水対応に関する公式記事)https://blog.x.company/what-its-like-to-set-up-balloon-powered-internet-during-a-flood-fb756210fae0
- SES / O3b Networks (2017). O3b Networks Works with Project Loon Team to Reconnect People Recovering from Floods in Peru. (ペルーでの復旧支援)
- X / 提携通信事業者各社による、ハリケーン「マリア」後プエルトリコでの接続提供に関する公式発表・技術ブログ(例:Connecting Puerto Rico 等)。
- Loon関連技術・運用の総括資料:The Loon Library(技術ホワイトペーパー集)※PDF、公的配布資料。
3. 後継技術・HAPS・Taara関連
- HAPS Alliance結成プレスリリース(2020年2月21日付:Loon LLC / HAPSMobile Inc.ほか)。
- Baris Erkmen (2021). Beaming Broadband Across the Congo River. Project Taara / X. https://x.company/blog/posts/taara-beaming-broadband-across-congo/
- Liquid Intelligent Technologies (2021). Wireless Optical Communication technology from Project Taara connecting Brazzaville and Kinshasa に関する公式リリース。
- SoftBank (2021). SoftBank Corp. Acquires High Altitude Platform Station Related Patents from Alphabet’s Loon LLC. (HAPS関連特許の継承)。
- Taara Connect, Inc. 公式情報(2025年スピンアウト後の事業概要)。