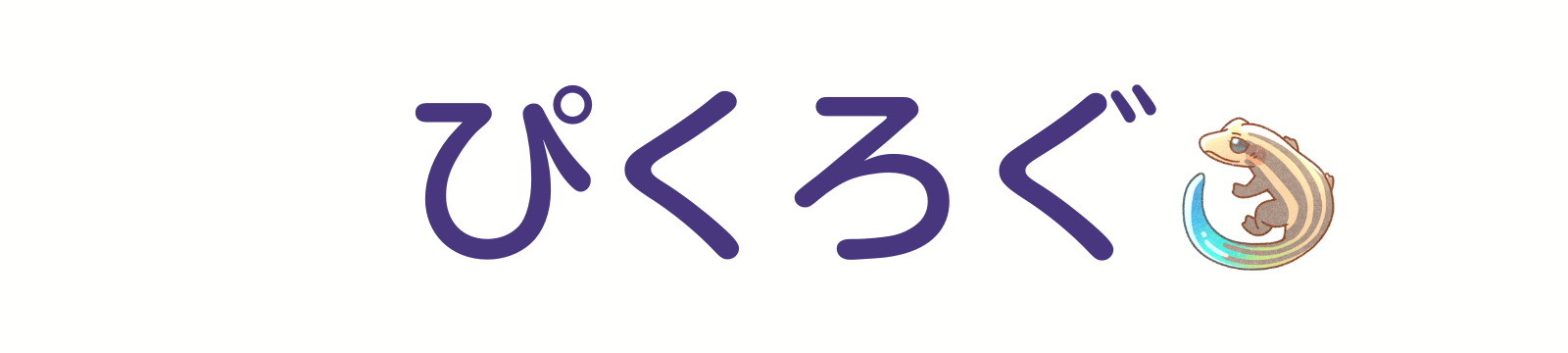ダイダロス計画。
あなたはまだ、その名を知らないかもしれません。
これは核融合で探査機を光速の一割余りまで押し上げ、
わずか半世紀で隣り合う星へ到達させる……
そんな「恒星間への最短ルート」を、1970年代の技術で本気で描いた工学設計です。
この記事では「50年で隣の星へ。」とばかりに、
1970年代、英国惑星間協会(BIS)がそれを工学的に語れる設計図まで描いた、
「その日」を目指した技術者たちの挑戦を追います。
ダイダロス計画とは?
ダイダロス計画とは、
1973〜1978年に英国惑星間協会(BIS)が実施した無人恒星間探査機の工学設計研究のことです。
核融合ロケットで光速の約12%(0.12c)まで加速し、
約50年でバーナード星(5.9光年)へ到達することを想定していました。
※バーナード星:へびつかい座の方向にあるM型の恒星。肉眼では見えない。
初期質量約5.4万トンの二段式融合推進。
約5万トンの燃料(重水素/ヘリウム3)を使い、第1段は約2.05年で0.071cへ。
第2段は約1.76年で最終0.12cへ押し上げ、その後約46年巡航します。
有人ではなく無人。目的は「人類が生きているうちに」データが地球へ届くことでした。
どんな未来像が描かれていたのか?
電子ビーム駆動ICF(慣性閉じ込め核融合)で毎秒250発の燃料ペレットを点火、
磁気ノズルでプラズマを整流して推力化するパルス融合エンジン。
減速は行わずフライバイ観測を前提に、到着の7.2〜1.8年前から18機のサブプローブを放出。
第2段の直径約40mのエンジンベルは、到着時には高利得通信アンテナとして転用されます。
と、専門用語を並べた難しい文章になってしまいましたが、
もし実現していたら、私たちの実生活はどのようになっていたでしょうか?
一言で言うと、「停電が減る・通信が速い・医療が頼もしい」といった、
日々の安心に直結していたことでしょう。
- 電気は今より止まりにくくなり、病院の機械は小さくて力持ちに。
- 橋やトンネルを見回る巡回ロボが当たり前になり、故障は早く見つかり早く直る。
- 山奥や離島でも通信が速く安定。時計がぴったり合うので自動運転やオンライン決済がより安心。
- 月の資源や宇宙工場で作った部品が、スマホや家電などのふつうの製品に当たり前に使われる。
- ニュースや教科書には隣の星の本物の写真が並び、宇宙の話が身近な日常になる。
なぜ未完に終わったのか
なぜ、未完に終わってしまったのでしょうか。
一言で言うと、「推進・資源・自律運用・費用」の4つの壁を、
国家レベルの長期コミットで越える枠組みが成立しなかったからです。
実はダイダロスは設計研究としては完了しています。
ですので、計画そのものが未完に終わってしまった(中止になった)というよりは、
上記の4つの壁によって実証段階へ進まなかったと捉えるのが正確かもしれません。
- 推進(ICF):毎秒250回の高繰り返し点火、長時間連続運転、電力回収・熱設計など
エンジンとしての成熟が未到達。 - 資源(He‑3):木星/月からのHe‑3大量採取という前提インフラ自体が超国家級プロジェクト。
- 自律運用:半世紀の無補給・自己修理・深宇宙通信など、
当時の計算機・材料・センサーでは信頼性の裏付けが薄かった。 - 費用・政治:数十年スパンでの国際的予算合意はハードルが高く、
観測データのために恒星間を正当化しにくかった。
その後の影響と現在への継承
ダイダロスは工学的に語れる恒星間の原点となり、比較基準として後継案を生みました。
そんな後継案は以下に。
- プロジェクト・イカロス(2009〜)
-
ダイダロスの再設計研究。
減速して留まる(ランデブー)可能性も議題にし、ICFや補助推進(磁気セイル等)を検討。 - プロジェクト・ロングショット(1988)
-
NASA/米海軍兵学校のICF推進・無人設計。
アルファ・ケンタウリへ約100年規模。 - スターライト(DEEP‑IN/DEIS)&ブレイクスルー・スターショット(2016〜)
-
地上レーザー×軽量ナノプローブで0.15〜0.2c級を狙う小さく・速く・多数の路線。
- 融合科学の進展
-
ICF点火の実証など進歩はあるが、推進用の高繰り返し・高効率・小型化は次世代の課題のまま。
年表
- 1973–1978:BISがダイダロスを実施(二段ICF・0.12c・約50年/バーナード星)。
- 1988:ロングショット(ICF・無人・約100年/アルファ・ケンタウリ)。
- 2009–:イカロス(ダイダロス再設計。到着後の観測継続を視野)。
- 2016–:スターショット(レーザー帆で0.2c級・数十年到達)。
まとめ
ダイダロスは到達のための課題地図を残しました。
工学的に「ここまで詰めれば届く」というのを初めて輪郭化し、どこが詰まるのかまで示したのです。
もし実現していたら?
一回の飛行で、赤い恒星バーナード星のわきをかすめ、
星のまわりを回る惑星や見えない磁気のバリア、宙に舞う細かなちりを、
1秒で地球をほぼ一周する速さで一気に撮り、
その一瞬を直径40メートルの巨大な皿アンテナで地球へ送り返していたかもしれません。
※バーナード星:へびつかい座の方向にあるM型の恒星。肉眼では見えない。
用語解説
- 慣性閉じ込め核融合(ICF)
-
小さな燃料ペレットをレーザー/電子ビーム等で一気に圧縮・加熱し点火する方式。
ダイダロスは電子ビームでの点火構想。 - ヘリウム3(He‑3)
-
D/He‑3反応の燃料。地球では希少で、木星大気や月からの採取が前提。
- 磁気ノズル
-
融合で生じた高温プラズマを磁場で整流し推力に変える装置。
- オリオン計画
-
機外で小型核爆発を連続起爆して推進板で受ける方式。内部点火ICFのダイダロスとは原理が異なる。
オリオン計画についてはこちら👇 - スターライト/スターショット
-
指向性エネルギー(レーザー)で超小型探査機を相対論的速度へ押す研究系譜。
FAQ
- 恒星間飛行は不可能?
-
物理法則が禁止しているわけではない。
エネルギー密度・推進効率・材料・費用の複合課題が未解決というのが現状。ダイダロスはどこが詰まるかを初めて地図化した。 - 減速しないなら意味がない?
-
フライバイでも、事前の望遠鏡観測とサブプローブの先行投入で
惑星・磁気圏・ダスト環境など一次データを得られる。目的は「留まる」ではなく「知る」ことであった。
- スタートレックの「ワープ」は現実的?
-
現状は理論仮説段階で、負のエネルギーなど非現実的要件が多い。
ダイダロス/スターショット系は既知の物理の延長で積み上げる路線。 - 6光年近く離れていて通信は可能?
-
直径約40mのエンジンベルを高利得アンテナに転用して電波通信する想定。
将来はレーザー通信や太陽重力レンズ焦点の活用も研究中。 - ペイロードは450トンか500トンか?
-
資料により表記ゆれがあるが、BISの要約では約450トンを科学プローブとして記述。
本文では約450トンに統一した。 - なぜ「バーナード星」を選んだのか?
-
「近い×惑星がありそう×生きているうちに成果」という三拍子がそろって見えたから。
※約50年で到達=人の人生のうちにデータが返ってくるという目算
参考文献・一次資料
- Project Daedalus — JBIS Supplement (1978):最終報告の収録。BISショップ/ADSに所在。
- Project Icarus(2010–):ダイダロス後継の再設計研究(JBIS/ArXiv)。
- Project Longshot(1988, NASA/USNA):ICF推進・無人・α Cenへ約100年案。
- Starlight(DEEP‑IN/DEIS, UCSB/NASA NIAC):指向性エネルギー推進の計画概要。
- Breakthrough Starshot(2016–):レーザー帆で0.2c級を狙う現行路線。