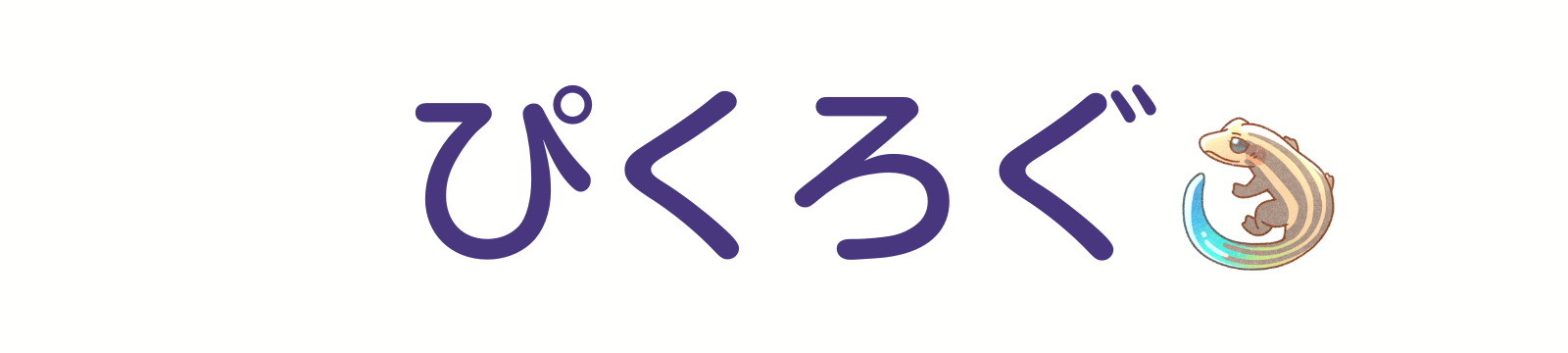人類の歴史の中には、目に見えないほど小さな「蚊」との戦いの歴史もあります。
特にマラリアは、今なお年間数十万人の命を奪う脅威です。有名な話ですね。
実は、かつて人類がこの宿敵を「地上から完全に消し去る」という
壮大な計画に乗り出した時代があったのです。
それが1955年に始まった
「世界マラリア根絶計画(Global Malaria Eradication Programme: GMEP)」です。
さて、この記事では、このプロジェクトの顛末を紹介していきます。
世界マラリア根絶計画(GMEP)とは?
それは地球上からマラリアによる在来感染(地域内で発生する感染)を根絶することを目的とした、
人類史上最大級の公衆衛生プロジェクトでした。
単なる流行の抑制(コントロール)ではなく、感染の連鎖を完全に断ち切り、
特定の地域から在来感染をゼロにすることを目指した点が画期的だったのです。
※用語注
根絶(eradication)は世界全体で在来感染をなくす概念、
排除(elimination)は特定国・地域で在来感染がゼロの状態を指します。
いつ・誰が・どこで・何を目指したのか
世界マラリア根絶計画(GMEP)は、
1955年に世界保健機関(WHO)の第8回世界保健総会(決議WHA8.30)で採択・開始されました。
主導したのはWHOです。
そして、加盟国政府、ユニセフ(UNICEF)や米国国際開発庁(USAID)などが資金・技術を提供。
対象は流行国全域で、とくにアジアとラテンアメリカで広域に実施されました。
最終目標は、屋内残留噴霧(IRS)などによりマラリア媒介蚊(主にハマダラカ属)による伝播を断ち、
各地域で在来感染をゼロにして世界的根絶を成功させることでした。
なぜ立ち上がったのか(当時の状況)
背景には二つの要因がありました。
一つは希望でした。
1940年代、強力な殺虫剤DDT※の効果が第二次世界大戦期の防疫などで実証され、
家屋の壁に噴霧するだけで蚊と患者が劇的に減る事例が相次いだのです。
この成功体験が「短期決戦で根絶できる」という楽観論を後押しするのも当然のことと言えます。
そして、もう一つは焦りです。
1950年代半ば以降、各地でDDT抵抗性(耐性)を持つ蚊の報告が増え始めたのです。
これはいけない、と「耐性が広がる前に一気に根絶へ」という危機感がGMEPを後押ししました。
※用語注
DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン):安価で残留性が高く、少量で高い殺虫効果を持つ有機塩素系殺虫剤。
国際がん研究機関(IARC)はヒトに対しておそらく発がん性(グループ2A)と分類しています。
GMEPの技術と仕組み
この計画は、国全体の家々を対象に、決められた手順と強力な薬剤を同時に使って進めるものでした。
成功のポイントは、DDTという薬だけに頼らずに状況を見ながら作戦を続け、
観察し、必要に応じて修正していく力にありました。
中核となる技術要素
GMEPの中核は屋内残留噴霧(Indoor Residual Spraying: IRS)でした。
ハマダラカは吸血後に室内壁面などで休息する習性があるので、それを利用すべく、
あらかじめ薬剤を処理した壁に接触させて死滅させるという戦略です。
同時に、当時の第一選択薬であったクロロキン等の治療で
ヒト側の感染源を減らす取り組みも併用されました。
※用語注
ハマダラカ:マラリア原虫を媒介する蚊の主要な属。
アフリカではガンビエハマダラカ(An. gambiae複合体)などが高い媒介能を示します。
どのように実現しようとしたか
WHOは、GMEPを準備期・攻撃期・強化(統合)期・維持期の4段階に区分して推進しました。
国家レベルで攻撃(介入)と監視を循環させる
→一定期間の無症例を確認して維持期へ移行
→在来感染ゼロの状態を長期に維持、という流れです。
(※国の「排除」認証は、少なくとも3年以上の在来感染ゼロが要件)。
GMEP「攻撃期」の戦略要件
- 使用薬剤:当初はDDT水和剤(のちに他系統薬剤へ切替・併用)
- 噴霧目標:対象地域の家屋≥80%の網羅
- 噴霧頻度:残留効果に応じて年1回〜2回
- 残留効果:壁面で概ね6か月程度を想定(気候・基材で変動)
- 作戦期間:少なくとも3〜4年連続の実施
- 評価指標:スライド陽性率(SPR)や発生率の急減、感染連鎖の遮断
世界マラリア根絶計画はなぜ未完に終わったのか
「単一の魔法の薬」による短期決戦は、生物学的適応と運用上の現実の壁に突き当たりました。
戦略の基盤が崩れたとき、依存の弱点が露呈したのです。
技術的・安全上の課題
最大の技術的な問題は、薬が効かなくなる「抵抗性」でした。
1950年代の後半からアジアやアフリカなどで、DDTが効かないハマダラカが次々に見つかります。
当然、室内に薬剤をまくIRSという方法の効果は弱まっていきました。
さらに、薬をまいた壁を避けて外で休むように行動を変える蚊も観察されたのです。
それだけではなく、安全面でも問題がありました。
レイチェル・カーソンの「沈黙の春」(1962年)は、
DDTが自然の中に残り、生き物の体にたまっていく危険を指摘しました。
これをきっかけに社会の批判が高まり、
1972年にはアメリカで一般的なDDTの使用が禁止されることになります。
政治的・経済的・社会的要因
もっとも苦労したのは、サハラ以南のアフリカでした。
広い地域にわたって交通や医療の仕組みが整っておらず、
すべての家を回って薬をまいてIRSを行き渡らせること自体が難しかったのです。
さらに、行政やお金の問題、人材の不足、
そして「家の中に入られるのが不安だ」と感じる住民の反発など、
さまざまな要因が重なって計画はうまく進みませんでした。
その結果、WHOは1969年の世界保健総会(WHA22.39)で、
「短期間で世界中からマラリアをなくすことは現実的ではない」と判断し、
根絶よりも「長く続けられる形でマラリアを抑える」方向へと方針を変えました。
世界マラリア根絶計画がもし実現していたら
歴史に「もし」はありません。
ですが、それでも。
もしGMEP(世界マラリア根絶計画)が成功していたなら、
救えた命の数や得られた社会的な利益は計り知れないものになっていたでしょう。
マラリアがなくなれば、医療費や仕事を休むことによる損失が減ります。
そして子どもの学びや人々の生産性が上がって、長期的な経済発展を後押ししたはずです。
実は、日本でも、かつてはマラリアが流行していました。
しかし戦後の公衆衛生の向上(室内での薬剤散布=IRSを含む)によって感染は急激に減少し、
沖縄では1962年にマラリアがなくなりました。
それ以降、日本国内で自然に感染するケースは報告されていません。
なお、WHOが正式に「マラリア排除国」として日本を認めたのは2012年です。
すでに長いあいだ国内感染がなかったため、形式的な確認として認証が行われました。
現代からの展望と課題
GMEPは最終的にマラリアを根絶することはできませんでしたが、
その経験は今の多面的な対策へとつながっています。
現在では、殺虫剤をしみこませた蚊帳(ITN)、
室内への薬剤噴霧(IRS)、すぐに結果がわかる検査(RDT)、
そしてアルテミシニンを使った併用治療(ACT)が基本セットになっています。
これに加えて、ワクチンも実用化されました。
RTS,S/AS01は2021年に、R21/Matrix-Mは2023年にWHOが推奨しています。
さらに、蚊の遺伝子を操作して病気の広がりを抑える「遺伝子ドライブ」など、
新しい技術の研究も進められています。
GMEPが残した最大の教訓は、「ひとつの技術に頼りすぎてはいけない」ということ、
そして「対策を続け、常に状況を見ながら改善することこそが本質である」という点にあります。
※用語注
遺伝子ドライブ:特定遺伝子を遺伝的に偏って次世代へ伝える仕組みを利用し、
標的集団の性比や繁殖を操作する技術。社会的・生態的リスク評価が前提となります。
年表
| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 1939年 | スイスの化学者パウル・ヘルマン・ミュラーがDDTの殺虫効果を発見。 |
| 1948年 | ミュラーがDDT発見の功績でノーベル生理学・医学賞を受賞。 |
| 1940年代 | 第二次世界大戦下でDDTが発疹チフス媒介シラミやマラリア媒介蚊の制圧に広く使用。 |
| 1955年 | WHO第8回世界保健総会がGMEP(WHA8.30)を採択。 |
| 1955〜60年代前半 | アジア・中南米でIRSと治療の大規模展開。多数の国で患者数が劇的に減少。 |
| 1950年代後半 | 各地でハマダラカのDDT抵抗性が公式報告として相次ぐ。 |
| 1962年 | レイチェル・カーソン『沈黙の春』刊行。環境リスクが国際的論点に。 |
| 1962年 | 沖縄でマラリア・フリー達成(日本本土でも戦後に在来感染は終息)。 |
| 1967–68年 | スリランカで再興流行(Resurgence)。1969年には50万例超を記録。 |
| 1969年 | WHO第22回総会(WHA22.39)で戦略を再検討。「根絶」から「防圧」へ軸足を移す。 |
| 1972年 | 米国でDDTの一般使用を禁止。 |
| 2012年 | WHOが日本のマラリア排除(Elimination)を公式認証。 |
| 2007年以降 | ゲイツ財団などが根絶研究投資を加速。ワクチンや遺伝子技術の開発が進展。 |
用語解説
- WHO(世界保健機関)
-
国連の専門機関の一つ。
すべての人々が可能な最高の健康水準に到達することを目的として設立。GMEPの主導機関。 - DDT
-
有機塩素系殺虫剤。残留性が高く、GMEPの当初の主軸。
IARCは「おそらく発がん性(2A)」に分類。 - ハマダラカ(Anopheles)
-
マラリア原虫を媒介する蚊の属。世界に約460種が知られ、そのうち約100種が媒介能を持つ。
- 屋内残留噴霧(IRS)
-
家屋内壁に殺虫剤を残留させる制御法。吸血後に屋内で休む蚊の習性を利用。
- マラリア原虫(Plasmodium)
-
マラリアの病原体。蚊の吸血で感染し、ヒト赤血球内で増殖。
- スライド陽性率(SPR)
-
顕微鏡検査した血液塗抹標本のうち原虫が検出された割合。流行状況の指標。
- 排除(Elimination)認証
-
WHOが付与。3年以上の在来感染ゼロを達成・証明した国・地域が対象。
FAQ
世界マラリア根絶計画(GMEP)はいつ始まったのですか?
1955年にWHOの世界保健総会決議(WHA8.30)で採択され、本格的に始動しました。
強力なIRSを中心に、世界的「根絶」を掲げた国際プロジェクトでした。
なぜマラリアはアフリカで特に多いのですか?
主に三つの理由です。
①媒介能の極めて高いガンビエハマダラカ群が生息
②一年中、蚊が活動できる気候
③医療・公衆衛生インフラの脆弱さ
日本にも昔マラリアはありましたか?
はい。沖縄や本州の湖沼地域などで流行がありました。
戦後の対策で在来感染は終息し、沖縄では1962年にマラリア・フリーに到達。
長年ゼロを維持したのち、WHOの排除認証は2012年に付与されています(輸入症例は除外)。
計画はなぜ中止(戦略転換)されたのですか?
主因は薬剤抵抗性の拡大と、広域での運用・資金・人材の持続性の不足です。
さらにDDTの環境・健康リスクへの懸念が社会的に高まりました。
1969年にWHOは「根絶」から防圧(コントロール)へ戦略を見直しました。
現在もマラリア根絶の研究は続いていますか?
はい。
ITN・IRS・RDT・ACTとワクチン(RTS,S・R21)を組み合わせる多面的戦略が主流で、
遺伝子ドライブなど次世代技術の研究も進行中です。
まとめ
- 結論:GMEPは1955年開始、IRSを主軸に世界的な在来感染ゼロを目指した国際プロジェクト。
- 戦略:DDT依存のIRS+診断・治療。網羅率≥80%と継続的監視が成否を分けた。
- 未完の理由:DDT抵抗性の拡大、環境・健康リスクの懸念、
アフリカでのインフラ・資金・行政の制約。1969年に「防圧」へ転換。 - 今日への遺産:一つの技術だけに頼るのは危険であり、常に状況を見て対策を続けていくことが大切。
こうした考え方は、現在のワクチン(RTS,SやR21)や遺伝子技術の研究にも受け継がれている。
GMEPは、希望と現実のはざまで揺れた「未完成の大きな計画」でした。
「根絶」自体は叶わなかったものの、その挑戦と失敗から得られた教訓こそが、
今の多面的なマラリア対策や、次の根絶に向けた取り組みの土台になっているのでしょう。
きっと、「根絶」できる日がやってくると、信じて。
参考資料・出典(一次情報・公的資料)
1. 計画の経緯・戦略
- World Health Assembly (1955). WHA8.30: Malaria Eradication.(WHO公式アーカイブ)
- World Health Assembly (1969). WHA22.39: Re-examination of the Global Strategy of Malaria Eradication.(WHO公式アーカイブ)
- Nájera JA, Gonzalez-Silva M, Alonso PL (2011). Some Lessons for the Future from the Global Malaria Eradication Programme (1955–1969). WHO/TDR 論文
- WHO (2017). Eradication of malaria. WHO Executive Board文書(WHA22.39等の位置づけを整理)
2. 技術的・環境的課題
- WHO Expert Committee on Insecticides (1960–61). Technical Report Series, No. 191 等(各地のDDT抵抗性報告を総括)
- Davidson G (1961). DDT-resistance in Anopheles stephensi. Bulletin of the WHO
- Carson R (1962). Silent Spring.(DDTの環境影響を社会問題化)
- US EPA (1972). DDT: Notice of Cancellation.(米国における一般使用禁止)
3. 日本・各国の排除・再興
- WHO Global Malaria Programme. Countries and territories certified malaria-free(日本の2012年認証を含む一覧)
- 外務省. 沖縄におけるマラリア対策の経過(1962年の沖縄マラリア・フリーに言及)
- Ministry of Health – Sri Lanka. Anti Malaria Campaign: History(1967–68年の再興流行)