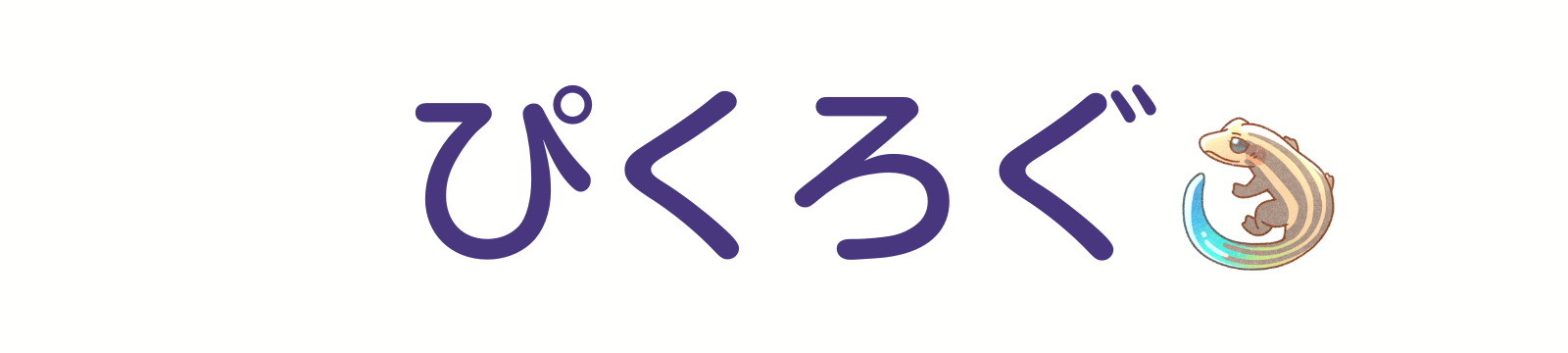月面都市計画。
あなたも耳にしたことがあることでしょう。
これはその名の通り、
月にある資源を活用し移動可能な居住施設を組み合わせることで、
「住む」から「暮らす」、そして「社会を営む」へと
段階的に発展させていく長期的な構想です。
さて、この記事では、凍てつくクレーターの縁から昇る太陽、その光が絶えず注ぐ南極の稜線、
そして深い闇の中に眠る太古の氷といった月面の情景を舞台に、
最初の居住棟が設置される「その日」を目指す技術者たちの挑戦を追います。
月面都市計画とは?(概要・背景)
月面都市計画とは、
月面に、一時的な観測拠点ではなく持続的な生活圏を築くための社会インフラ整備の総称です。
なお、単独の計画名ではないのです。
アポロ計画後に各国宇宙機関や企業が提案してきた複数の構想が含まれています。
ねらいは、科学探査の高度化、ISRU(現地資源利用)による水・酸素・推進剤の自給、
そして火星有人探査へ向けた中継基盤の確立した。
※用語注:ISRU=In‑Situ Resource Utilization(現地資源利用)。
輸送依存を減らすため、探査先の資源をその場で利用する技術です。
いつ・誰が・どこで・何を目指したのか
起点は1960〜70年代の米ソによる有人月面計画の余波にあります。
21世紀に入ってからは、NASA・ESA・JAXA・CSAなどの公的機関に加え、産業界も参加しました。
建設候補は月極域(とくに南極域)です。
それは、水氷の存在や長時間日照域の活用可能性が示されているためです。
最終像は、地球依存を下げた常駐型の居住・研究・産業拠点です。
なぜ立ち上がったのか(当時の状況)
技術的背景に加え、月に水資源があるということが決定打になりました。
2009年のLCROSS+LROの協調観測で南極カベウスに水氷が直接示され、
2020年にはSOFIAが日向面にも分子状水を確認しました。
「水」は飲料・酸素・推進剤に転化できるため、現地自給の現実味が増したのです。
月面都市計画の技術と仕組み
月は真空・低重力・高線量・極端温度差という「地球の常識が通じない」環境です。
生存と運用を両立させる鍵は、地産地消×高信頼性の設計にありました。
電力・遮蔽・水/酸素・移動・通信・在地製造を束ねて、補給の谷を埋めようとしたのです。
中核となる技術要素
- 居住モジュールと遮蔽:レゴリスで覆土し、宇宙線・微小隕石から守る。
- 生命維持システム:空気・水の再生循環と、故障時の冗長化。
- ISRU(資源):氷からの水・酸素生成、レゴリスからの酸素抽出、建材製造。
- 電力:極域の長時間日照域ソーラー+小型核分裂電源(〜40 kWe級)でベースロードを確保。
- 移動・物流:与圧ローバーで広域移動と輸送。将来は無人搬送と連携。
- 建設・製造:レゴリス3Dプリントや焼結、就地保全(ISAM)で補修・増築を可能に。
※用語注:レゴリス=月表面の砂・塵・砕屑岩の層。鋭利で付着性が高く、装備や健康に影響します。
どのように実現しようとしたか
初期は地球から居住・発電・掘削装置を搬入し、レゴリス被覆で遮蔽します。
水と酸素は、極域氷の採掘+精製や、
レゴリスからの高温還元(カーボサーマル)や溶融電解(MRE)で賄います。
電力は長時間日照域に展開したソーラーで基礎負荷を担い、
小型原子炉で日照ギャップを埋め、
蓄電と合わせて安定化します。
移動は与圧ローバーが要で、極域の長距離巡航と物資回送を担います。
※用語注:カーボサーマル還元=レゴリスを高温で処理し、酸素をCO/CO₂として取り出す方式。
MRE=Molten Regolith Electrolysis(溶融レゴリス電解)。
月面拠点の基礎要件
・遮蔽:レゴリス被覆 2–3 m(宇宙線・微小隕石対策)
・電力:≥ 数十 kW、拠点規模で 100 kW 級(長時間日照ソーラー+40 kWe 級核分裂)
・移動:ミッション累計 1万 km 級(与圧ローバーの設計目標)
・資源:ISRUで水/酸素/建材を現地調達
・通信:片道約1.3秒の遅延を前提に自律運用を強化
月面都市計画はなぜ未完に終わったのか
月面都市計画が進まなかった主な理由は、
お金と運営の仕組み(ガバナンス)を長く安定して回せなかったからです。
放射線・粉塵・極端な温度差への対策には重たい装備と大量の電力が必要で、
補給の費用が一気に高くなります。
さらに、資源の扱い・安全基準・責任分担などの国際ルール作りも欠かせません。
しかし、政治は数年単位で方針が変わるのに、拠点づくりは数十年単位。
この時間感覚のズレが、計画を「未完」のまま引き延ばしてしまうことになります。
技術的・安全上の課題
月の放射線は「常時致死」ではありませんが、
積み重なる被ばくが大きな制約になります(約1.3 mSv/日の報告)。
そのため、しっかりした遮蔽と運用管理が欠かせません。
さらに、レゴリス(細かい砂ぼこり)は機器を痛め、吸い込むと健康にも悪影響が出ます。
粉塵の遮断・除染に手間がかかるうえ、
資源利用(ISRU)では約1600℃の高温で連続稼働でき、
しかも腐食に強い材料が必要という、難しい条件が残っています。
政治的・経済的・社会的要因
冷戦後は「月へ行く強い理由」が弱まり、予算の優先順位が揺れました。
現在はアルテミス合意で費用とリスクを分け合う枠組みが進む一方、
各国の利害調整や輸出管理・安全保障との整合が新たなハードルとなっています。
また、産業面においては、原子炉・推進・ロボット・蓄電といった供給網を
スケールアップできる体制づくりが求められています。
もし、月面都市計画が実現していたら
月面都市に明かりがともっていたら、
科学だけでなく、経済や文明のバックアップ力が一段上がっていたことでしょう。
月で水・酸素・推進剤を作って回す宇宙向けの供給網ができるので、、
地球近傍の輸送コストの考え方が変わります。
さらに、閉じた環境で資源を循環させる技術は、地球の資源・環境問題にもそのまま役立ちます。
また、月が火星や小惑星へ向かうための中継拠点にもなり「宇宙」がもっと広がったかもしれません。
当時描かれていた未来像
月は研究の最前線であり、ヘリウム3や金属資源の採掘拠点、低重力製造の試験場、
そして観光地として語られてきました。
最終的には、地球で大災害が起きたときの文明のバックアップとして機能させる構想もあったのです。
※注意:ヘリウム3発電は未検証で、回収・濃縮・炉の設計に不確実性が大きい
現代から見た波及の可能性
現在の技術水準を踏まえると、小規模拠点→拡張モジュールと段階的に広げるのが現実的です。
与圧ローバーでの広域探査・輸送、
40 kWe級の小型原子炉+蓄電、氷の処理と酸素製造を組み合わせれば、
2030年代に常駐に近い運用が見えてきます。
数千人という都市規模はまだ先ですが、拠点規模(数〜十数人)なら手の届く範囲に入っています。
年表
- 1969-07:アポロ11号、人類初の月面着陸。
- 1972-12:アポロ17号が帰還、アポロ計画終了。
- 2009-10:LCROSSが南極カベウスへ衝突、LROと協調で噴出物を観測。水氷の存在を直接示唆。
- 2010-10:NASAがLCROSS/LROの成果を整理、公表。
- 2007-2009:日本のかぐや(SELENE)が極域の地形・照度解析に寄与。
- 2013-12:嫦娥3号が月面着陸、以後の中国月探査に弾み。
- 2019-01:嫦娥4号が世界初の月裏側着陸。
- 2020-10:SOFIAが日向面の分子状水を報告。
- 2022-11:アルテミスI(無人)成功。
- 2026-04(予定):アルテミスII(有人月周回)。
- 2027年頃(予定):アルテミスIII(有人月面着陸)に後ろ倒し。
- 2030年代前半(構想):JAXA×トヨタ「ルナクルーザー」本格運用を視野。
用語解説
- 長時間日照域
-
極域の稜線など、年間を通じて日照率が高い地点の総称。
完全な「永遠の光」は稀で、90%前後の高照度点が現実的。 - 与圧ローバー
-
内部を地上と同等の気圧に保つ移動体。宇宙服を脱いだまま長距離移動・作業ができる。
- Fission Surface Power(FSP)
-
月面用の小型核分裂電源。40 kWe級を想定した設計研究が進んでいる。
FAQ
- 月面都市計画はいつ始まった?
-
発想自体はアポロ直後からありました。
本格化したのは2009年の水資源の手がかり以降です。
アルテミス計画の枠組みで現実味が増しました。 - なぜ中止(未完)のまま?
-
費用・線量・粉塵・電力・補給というボトルネックに対し、政治・予算サイクルが短いからです。
また国際的なルール実装も時間を要するためです。 - 現在も研究は続いている?
-
はい。
アルテミスII/III、FSP 40 kWe、与圧ローバー、氷処理×酸素製造など、
拠点実現に直結する開発が並行しています。 - 月に住めるのは何年後?
-
拠点(数〜十数人)の常続運用は2030年代が現実的な射程です。
都市規模はさらに数十年先と見込まれます(※推定)。
- 月に住むメリットは?
-
科学(地質・天体物理)、宇宙輸送のコスト構造転換、地球環境技術へのスピンオフ、
そして文明の冗長性です。 - 月面都市の持続可能なエネルギーシステムはなに?
-
極域の長時間日照域ソーラーを主電源にし、
小型核分裂電源と蓄電で日照ギャップを埋める方式が有力です。太陽光はクリーンで拡張しやすく、
原子炉は天候や夜間に左右されないためです。 - 月面基地の生活環境に必要なインフラ技術は何か?
-
遮蔽(レゴリス被覆)
空気水の循環(生命維持)
電力(ソーラー+原子炉)
通信(片道約1.3秒)
移動(与圧ローバー)
在地製造(3Dプリント/修繕)
これらが基盤です。
これらを多重化して、故障時も止まらない設計にします。※用語注:与圧ローバー=内部を地上並みの気圧に保つ乗り物。
- 月面での水資源の利用とその課題は?
-
極域の氷を採掘・精製し、飲料・酸素・推進剤へ転用します。
課題:超低温の永久影での採掘・粉塵対策、
水の輸送や貯蔵・装置の耐久性など運用負荷が高いこと。 - 月面都市の設計における健康維持の工夫は?
-
ポイントは「守る・鍛える・整える・支える」です。
- 守る:放射線を遮るためにレゴリス被覆などで居住区を厚く覆います。
粉塵(レゴリス)は機器と肺に悪いので、気密ドアや除塵ルームを設けて持ち込みを防ぎます。 - 鍛える:低重力で骨や筋肉が弱りやすいので、
レジスタンス運動やトレッドミルを毎日ルーチン化することになります。 - 整える:空気と水を循環させ、
CO₂・湿度・温度・騒音・照明(体内時計用の昼夜サイクル)を細かく管理します。 - 支える:メンタルケア(緑化・個室・交流設計)、食事の栄養最適化、
遠隔医療と救急プロトコル、感染対策を標準装備にします。
そう、月は真空・低重力・高線量・極端な温度差で補給も高コストになってしまいます。
地球の都市が外の自然を前提にするのに対し、
月面都市は閉じた循環と在地製造を前提にした安全と維持運用が設計の中心になります。 - 守る:放射線を遮るためにレゴリス被覆などで居住区を厚く覆います。
まとめ
- ねらい:観測地から生活圏へ
- 核:遮蔽/電力(ソーラー+原子炉)/ISRU
- 未完理由:技術の壁+社会・予算の壁
- 実現インパクト:宇宙資源供給網/科学の大きな進歩/文明のバックアップ力
月面都市計画は、地球という揺りかごの外で暮らすための「設計図」です。
いま現実味があるのは小さな拠点づくりで、本格的な都市はまだ先です。
とはいえ、電力・資源・移動の体制がそろえば、
月も地球のように人が働き、眠り、また活動を始める日常の場所へと変わるでしょう。
参考資料・出典(一次情報・公的資料)
観測・科学
1.NASA(2019–2010)『LCROSS / LRO 水氷検出関連』公式リリース/ヒストリー資料。
2.Honniball, C. ほか(2020)『SOFIAが日向面の月で水を検出』NASAリリース。
3.Hayne, P. O. ほか(2020/2021)“Micro cold traps on the Moon.” Nature Astronomy 5, 169–175.
DOI: 10.1038/s41550-020-1198-9。
4.Zhang, S. ほか(2020)“First measurements of the radiation dose on the lunar surface.” Science Advances(PMC公開版)。
拠点計画・電力
5. NASA(2025)『Artemis II / III タイムライン更新』FAQ・ニュース。目標:Artemis II = 2026-04 以降、Artemis III = 2027年頃。
6. Oleson, S. ほか(2022)“A Deployable 40 kWe Lunar Fission Surface Power Concept.” NASA NTRS(論文PDF)。
7. NASA(2023)“Overview of NASA Fission Surface Power.”(NETS 2023資料)。
ISRU(資源)
8. NASA(2020–2025)“Oxygen from Regolith.”:カーボサーマル還元・MREの概説と試験。
NTRS/TechPort資料(Sibille 2020; Jones 2020; CaRD/CTOP/COPR関連)。
9. Haggerty, N.(2025)“Environmental Testing of a Fully Automated Carbothermal Oxygen Production Reactor(COPR).” NTRS(PDF)。
10. Grossman, K.(2020)“Development of a Cold‑Walled Molten Regolith Electrolysis Reactor.” NTRS。
移動・ローバー
11. JAXA × トヨタ(2020–)『与圧ローバー “LUNAR CRUISER”』プレス
12. JAXA(2024)『Lunar Surface Exploration Implementing Arrangement』与圧ローバー解説(英)。
照度・立地
13. NASA/GSFC(2022)『南極照度シミュレーション(2023–2030)』可視化ページ。長時間日照域の存在。
14. Fincannon, J.(2007)“Lunar South Pole Illumination.” NASA Glenn(PDF)。