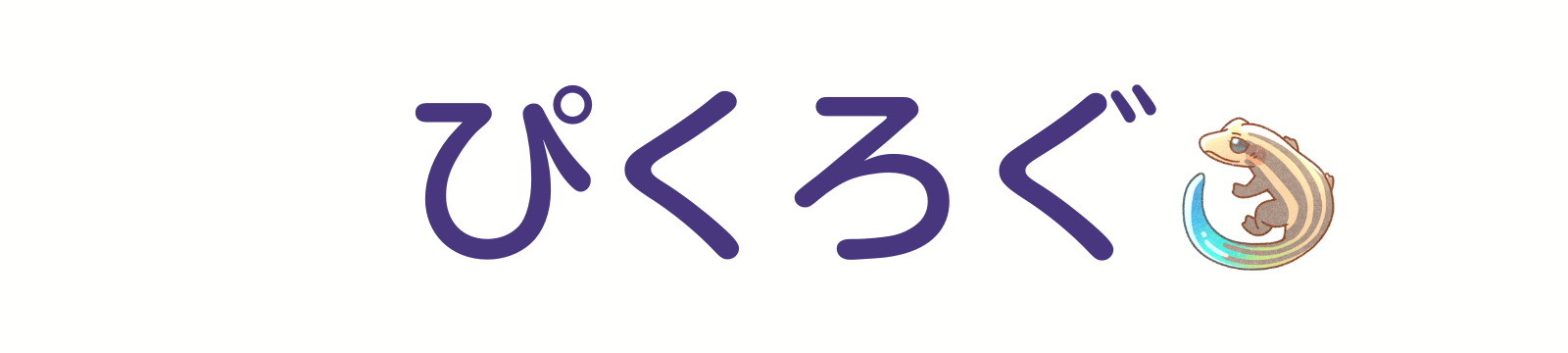子どもの健康は、どこまで環境に左右されるのか?
そう考えたことのある人は少なくないでしょう。
かつてアメリカでは、その答えを調査するために、
10万人の子どもを出生前から21歳まで追うプロジェクトを遂行したことがあります。
それが、全米小児研究(NCS)です。
家庭の空気や水、臍帯血や胎便まで、見えない曝露を徹底的に測る試みでした。
しかし、代表性と実務の両立、膨らむ費用という現実の前に、計画は歩みを止めます。
残されたデータと学びは、後継のECHOへ受け渡されました。
全米小児研究(National Children’s Study)とは?
未来の世代が直面する健康問題の「なぜ」を、
誕生の瞬間から解き明かそうとしたプロジェクト。
それが「全米小児研究(National Children’s Study: NCS)」です。
この研究はアメリカ合衆国が計画した、
国内史上最大規模となるはずだった出生コホート研究プロジェクトでした。
環境が子どもの健康と発達に与える複雑な影響を、
10万人の子どもたちを出生前から21歳になるまで
追跡することで解明するという、前例のない野心的な試みでした。
もし完遂していれば、現代医学の教科書を書き換えるほどの知見をもたらしたかもしれません。
しかしながら、その壮大さゆえに、計画は道半ばで大きな壁に直面しました。
※用語注
出生コホート研究:特定の地域や集団(コホート)を長期間にわたり追跡調査し、
病気の原因や健康への影響要因を探る疫学研究の手法。
いつ・誰が・どこで・何を目指したのか
全米小児研究(NCS)は、2000年に米国議会で
「子どもの健康法(Children’s Health Act of 2000)」が成立したことを受け、公式に始まりました。
研究を主導したのは、米国の医学研究の総本山である国立衛生研究所(NIH)内の、
ユーニス・ケネディ・シュライバー国立小児保健・人間発達研究所(NICHD)です。
さらに、CDC(疾病予防管理センター)やEPA(環境保護庁)も計画段階から連携しました。
全米では統計学的に抽出された105の調査地域(Study Locations/PSU)が設定され、
そこを舞台に妊婦とその子どもたち10万人を募集し、追跡調査を行う計画でした。
そして、最終的な目標は、
「環境要因が、喘息、自閉症、肥満、糖尿病、学習障害といった小児疾患や発達にどのような影響を与えるか」
という根本的な問いに、決定的な答えを出すことでした。
※用語注
PSU(Primary Sampling Unit):NCSの第1段階サンプリングで抽出された基礎単位で、
一般に単一郡(County)またはその集合を指す。
なぜ立ち上がったのか?当時の状況は?
計画が立ち上がった1990年代後半から2000年代初頭のアメリカは、
子どもの健康をめぐる「静かな危機」に直面していました。
というのは、実は当時、
喘息、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、
肥満、学習障害などの有病率が、
明確な理由が分からないまま増加傾向にあると報告されていたのです。
これらの疾患の多くは、遺伝的要因だけでは説明がつかず、
日常生活で曝露される化学物質、栄養状態、社会的ストレスといった
「環境要因」が複雑に関与しているのではないかと強く疑われていました。
しかし、それを証明するための大規模で信頼性の高いデータが決定的に不足していたのです。
NCSは、このブラックボックスを解明し、
未来の子どもたちを守るための科学的根拠(エビデンス)を確立する、
という国家的な要請を受けて誕生しました。
全米小児研究の技術と仕組み
この大がかりな調査は、「環境」と「健康」の関係を、
これまでの疫学調査よりもずっと細かく明らかにしようとしたものです。
ゆえに、人々の暮らしの中に入り込み、
ふだんは気づかないような要因までデータとして集めようとしました。
そのためには、全米規模でのサンプル(調査対象)集めと、
集めた膨大な情報をまとめて管理できるシステムが必要でした。
血液や尿といった体の検査データだけでなく、家のほこり、水道水、
さらに家族の経済状況など、子どもを取り巻くあらゆる環境を記録しようとしたのです。
中核となる技術要素
NCSの中心となる技術は、
「環境へのさらされ方を正確に測ること」と
「大規模に生体試料を保存すること」にありました。
研究チームは、これまでのように質問票で生活習慣を聞くだけでなく、
子どもたちが実際にどんなものを吸い込み、
どんなものに触れているのかを直接調べようとしたのです。
そのために、妊婦の血液、尿、母乳、毛髪、へその緒の血液などを集め、
冷凍して保存する「バイオバンキング」を行いました。
また、家庭の空気や水、ほこりのサンプルも採取し、
微量な化学物質まで検出できる最新の分析技術を使う計画でした。
これらのデータを、全国で10万人もの人から長期間にわたって同じ方法で集め、
管理する仕組みこそが、NCSの技術の中心だったのです。
どのように実現しようとしたか
NCSでは、まず全米から統計的に選ばれた105の地域(Study Locations)を
決めることから始まりました。
次に、その地域内の産科クリニックなどを通して妊婦を募集し、
研究の目的を説明したうえで参加に同意してもらう計画でした。
最初の段階では、研究員が家庭を一軒ずつ訪ねる方法(戸別訪問)によって
無作為に参加者を選ぶ案も検討されました。
そして、2009年に始まった試験的な調査(Vanguard Study)で、
この戸別訪問モデルが実際に試されました。
参加が決まった妊婦は、出産前から定期的に調査を受けます。
血液や尿などの生体サンプル、家の空気・水・ほこりなどの環境サンプルが集められ、
同時に保護者には質問票が配られました。
質問内容は、食事や生活習慣や精神的なストレス、家計の状況など、
子どもを取り巻く幅広い要因に関するものです。
こうして集まった大量のデータは、中央のデータセンターにまとめられ、
厳重なプライバシー保護のもとで分析される仕組みになっていました。
計画された調査の規模
- 対象人数:100,000人の米国の子どもたち
- 追跡期間:出生前(妊娠中)から21歳まで
- 調査地域:全米105カ所の調査地域(=PSU)。Vanguard(パイロット)はこのうちの拠点群であり、105地域そのものを指す用語ではない。
- 収集サンプル(例):血液、尿、母乳、毛髪、臍帯血、胎便(meconium)
- 環境サンプル(例):家庭内の空気、水道水、床や家具の埃
- 収集データ(例):健康診断結果、質問票(食事、生活習慣、心理、社会環境)
全米小児研究はなぜ未完に終わったのか
どんなに立派な理想を掲げた計画でも、
「本当に実行できるのか」という現実の壁からは逃れられません。
NCSも、そのあまりに大きすぎる規模、
そしてこれまでにないほど複雑な仕組みのために、
多くの困難にぶつかりました。
最初に描かれた計画どおりに進めることがだんだん難しくなり、
科学者たちの期待と、増え続ける費用や技術上の問題とのあいだで、
プロジェクトは揺れ動くことになります。
最終的には、「このままでは実行できない」という厳しい判断が下されてしまうことになります。
技術的・安全上の課題
NCSが直面した最大の技術的課題は、「参加者の募集(リクルート)」という根本的な問題でした。当初計画していた、地域住民の家を直接訪問して妊婦を探し出す方法(戸別訪問モデル)は、コストがかかりすぎるうえに効率が悪いことがVanguardの初期運用で明らかになりました。2010年以降は、医療提供者経由(Provider-Based Recruitment/Provider-Based Sampling)のサブスタディが段階的に導入され、病院・産科クリニック・出産施設を軸にしたリクルートが検証されましたが、地理ベースの代表性(確率標本)との両立が難しいという課題も露呈しました。さらに、10万人規模の多様な生体・環境サンプルを20年以上にわたり同品質で収集・保存し続ける標準化は、現実的に極めて困難でした。
※用語注
Provider-Based Recruitment(Sampling):
地域内の医療機関(産科・小児科等)をサンプリング枠として参加者をリクルートする方法。
NCSでは2012年前後にサブスタディとして本格検証が行われた。
政治的・経済的・社会的要因
NCSの最後の運命を決めたのは、経済と政治の現実でした。
計画にかかる費用は当初の見積もりを大きく上回り、
2008年の金融危機以降、アメリカ政府は厳しい財政状況に陥りました。
その結果、
NCSのような巨額の予算を必要とする大型プロジェクトは、次第に批判の的となっていきます。
さらに、研究の進め方そのものについても、
国立衛生研究所(NIH)の内部だけでなく、
米国医学研究所(IOM)や全米研究評議会(NRC)といった外部の専門機関からも
「計画が適切かどうか」に疑問の声が相次ぎました。
設計変更が何度も繰り返されたことで、現場は混乱し、科学的な信頼性にも疑いが生まれました。
そして2014年12月12日。
NIHのフランシス・コリンズ所長が、
NCSの中心となる「メイン・スタディ(Main Study)」の中止を正式に発表しました。
全米小児研究を完遂していたら
もしNCSが10万人の子どもたちを最後まで追跡できていたなら、
私たちは今、病気の「予防」をまったく新しいレベルで考えられていたかもしれません。
たとえば、ある化学物質が自閉症のリスクにどう関わるのか、
子どものころの栄養状態が大人になってからの糖尿病リスクにどう影響するのか?
これまで「関係がありそう」としか言えなかった多くのつながりを、
「原因と結果」としてはっきり示せるようになる可能性がありました。
当時描かれていた未来像
NCSの研究者たちが思い描いていたのは、
「科学的根拠(エビデンス)にもとづいた子育て」が当たり前になる未来でした。
たとえば、
「この地域の水道水に含まれる微量な物質が、子どもの神経の発達にこれだけ影響している」
といった具体的なリスクが明らかになるかもしれない、という構想です。
そうした知見をもとに、国はより厳しい環境基準を定め、
親たちはより安全な生活環境を選べるようになります。
もし、家の中のどんな要因が喘息やアレルギーを引き起こすのかが分かれば、
住宅の建材や設計の基準そのものが変わっていたかもしれません。
病気になってから治すのではなく、病気になる「リスク」を生まれる前から減らしていく。
NCSは、そんな究極の予防医学の実現を目指していたのです。
現代からの展望と課題
NCSは中止されましたが、その理念と成果は失われませんでした。
試験的に行われたVanguard調査で集められたデータや試料はすべて保管され、
延べ1万4千人以上、約5,000の家族、
40の地域から得られた生体・環境サンプルが、今も研究者に利用されています。
そして、その経験と教訓は、2015年に始まった後継プロジェクトである
「ECHO(Environmental influences on Child Health Outcomes)」に受け継がれました。
ECHOは、NCSのように一から大規模な集団を作るのではなく、
すでにある多くの研究グループ(コホート)をつなぎ合わせて分析する
「コホート・コンソーシアム」という仕組みを採用しています。
これにより、現実的に運用しやすく、
かつ科学的にも高い価値を保つことができるようになりました。
NCSの失敗は、
「壮大な科学の夢を実現するには、理想だけでなく、
計画と予算の現実的なバランスが欠かせない」
ということをはっきり示した例になりました。
年表
| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 2000年10月 | 「子どもの健康法(Children’s Health Act of 2000)」が米国議会で可決・成立。NCSの法的根拠が整う。 |
| 2004年 | NIHがNCSの実施計画(Research Plan)の草案を公表。 |
| 2005年 | パイロット拠点(Vanguard Centers)の選定を開始。 |
| 2008年 | 全米医学研究所(IOM)/全米研究評議会(NRC)が研究計画のレビュー報告書(2008年版)を公表。 |
| 2009年1月 | Vanguardの最初の2地域(ノースカロライナ州デュプリン郡/ニューヨーク市クイーンズ)で現地運用開始。 |
| 2010~2012年 | 戸別訪問モデルの非効率が判明し、Provider-Based Recruitment/Provider-Based Samplingのサブスタディを段階導入。 |
| 2013年 | 研究デザインの大幅な見直し案(いわゆるNCS-2)が提起される。 |
| 2014年6月 | IOM/NRC合同委員会が「現行計画では主要目的の達成は困難」と結論する決定的評価報告書を公表。 |
| 2014年12月12日 | NIH所長がNCSの主研究(Main Study)の中止を正式発表。 |
| 2015年 | 後継のECHOプログラムが始動(既存コホート連携型) |
用語解説
- 出生コホート研究 (Birth Cohort Study)
-
同じ時期に生まれた人々の集団(コホート)を対象に、
出生前から長期間(場合によっては生涯)にわたり、
健康状態や生活環境、疾患の発生などを追跡調査する疫学研究の手法。成長の過程でどのような要因が健康に影響するかを調べるのに
最も強力な研究デザインの一つとされる。 - 環境要因 (Environmental Factors)
-
遺伝的要因(生まれ持った体質)以外の、個人の健康に影響を与えうるすべての外的要因。
化学物質(農薬、大気汚染物質、鉛など)、
生物学的要因(感染症、腸内細菌など)、
物理的要因(放射線、騒音など)、
社会的・経済的要因(貧困、ストレス、教育、栄養状態)など、
非常に広範な概念をさす。 - バイオバンキング (Biobanking)
-
血液、尿、組織、DNAといった生体サンプルを、
将来の研究利用のために大規模かつ体系的に収集・冷凍保存し、
関連する医療情報や生活習慣情報と共に管理する仕組み。NCSにおいて、環境曝露と健康影響の関連を後からでも検証できるようにするために不可欠な技術だった。
- ECHOプログラム (Environmental influences on Child Health Outcomes Program)
-
NCSの中止後にNIHが立ち上げた後継プロジェクト。
全米の既存の小児コホート研究を連携させ、
標準化された手法でデータを追加収集・統合することで、
NCSが目指した「環境と子どもの健康」に関する問いに答えようとする、
より現実的なアプローチの研究プログラム。
FAQ
全米小児研究(NCS)はいつ始まったのですか?
法律的な承認は2000年の「子どもの健康法」成立時にさかのぼります。
現地でのパイロット調査(Vanguard Study)の最初の運用は
2009年1月(デュプリン郡/クイーンズ)に開始され、
その後、拠点と方式を拡大しつつ検証が続きました。
なぜNCSは中止されたのですか?
主な理由は、計画が壮大すぎて「実行不可能」と判断されたためです。
具体的には、10万人の妊婦を統計学的に正しく募集する方法の確立が難航したこと、
予算が当初の見積もりを大幅に超え続けたこと、
研究デザインをめぐる専門家評価で厳しい結論が示されたことなどが挙げられます。
2014年にNIHが最終的な中止を決定しました。
NCSの研究は現在も別の形で続いていますか?
はい。
NCSは中止されましたが、その理念と目的は2015年に開始された
「ECHO(Environmental influences on Child Health Outcomes)プログラム」に引き継がれています。
ECHOは、既存コホートを束ねる現実的な方法で「環境と子どもの健康」の関係を研究しています。Vanguard期に収集されたデータと試料も研究者向けにアーカイブ化されています。
まとめ
- 結論:全米小児研究(NCS)は、環境が子どもの健康に与える影響を解明するため、
10万人の子どもを21年間追跡する米国史上最大の出生コホート研究計画だった。 - 目的:喘息、自閉症、肥満などの小児疾患の増加に対し、
化学物質、栄養、社会的要因といった「環境要因」がどう関わっているかを突き止めること。 - 未完の理由:代表性と実務効率の両立が困難(戸別訪問→医療提供者経由への転換も十分機能せず)、
コスト膨張、設計変更の連鎖により、2014年にNIHが中止を決定。 - 未来インパクト:理念と資産はECHOに継承。
Vanguardで収集されたデータ/試料は公開基盤で活用され、
より現実的な連携型コホート研究へ発展している。
全米小児研究(NCS)は、壮大な理想を掲げながらも、
現実とのギャップに押しつぶされた「未完のプロジェクト」でもあります。
10万人の子どもたちを一生にわたって追いかけるという計画は、
確かにあまりにも大きな夢だったのかもしれません。
それでも、この挑戦と失敗から生まれた知見や経験は、
より現実的で続けやすい次世代の研究、
ECHOプログラムへと受け継がれました。
この研究の成果はきっと生かされていくことでしょう。
……もしNCSが計画どおりに最後まで実現していたなら、
今、私たちが信じている「子育て」や「公衆衛生」の常識は、
まったく違う形になっていたかもしれませんね。
参考資料・出典
【米国政府・公的機関報告書】
- U.S. Congress (2000). Children’s Health Act of 2000 (Public Law 106-310)(条文全文:govinfo.gov)。
- NIH(2014年12月12日).NIH Director Statement on the National Children’s Study (NCS)(NCS主研究の中止発表)。
- IOM/NRC(2014).The National Children’s Study 2014: An Assessment(決定的な外部評価報告書)。
【学術論文・総説(査読済み)】
- Landrigan, P. J., et al. (2006). The National Children’s Study: a 21-year prospective study of 100,000 American children. Pediatrics, 118(5), 2173–2186.
- Hirschfeld, S., et al. (2011). National Children’s Study: Status in 2010. Curr Opin Pediatr, 23(2), 188–194(CDC/EPAとの連携を含む初期状況の総説)。
- Annett, R. D., et al. (2016). The National Children’s Study: Introduction & Historical Overview. Pediatrics 137(Suppl 4)(105地域の抽出経緯)。
- Baker, D., et al. (2014). Recruitment of Women in the NCS Initial Vanguard Study. Am J Epidemiol, 179(11), 1366–1375(2009年開始地点の詳細)。
- Belanger, K., et al. (2013). Provider-based sampling for the NCS. Paediatr Perinat Epidemiol(医療提供者経由サンプリングの提案・検証)。
【後継プロジェクト(ECHO)】
- NIH ECHO Program(公式サイト:nih.gov/echo)— ECHOの構成と目的。
- LeWinn, K. Z., et al. (2021). The ECHO Program overview. Psychosomatic Medicine / PMC(複数コホート統合の概要)。
- NICHD(2020). NCS Archive Study Description/NOT-HD-20-018(アーカイブ化、収集試料の内訳:血液・尿・唾液・母乳・臍帯・胎便・埃・水・空気など)。