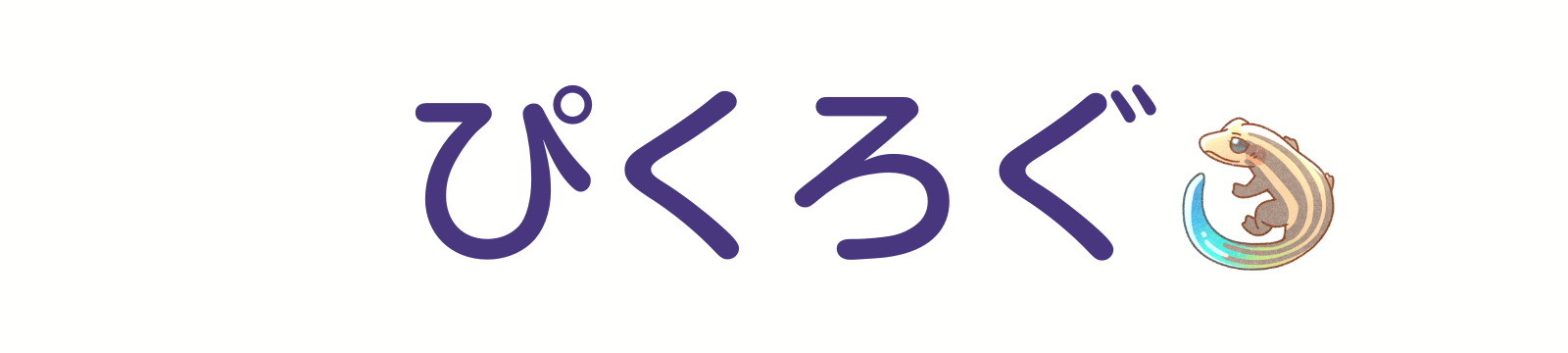果てしない空を、一度も地上に降りることなく飛び続けられたなら。
そんな究極の夢を追い求めたのが「原子力飛行機」計画です。
それは原子の火を翼に宿し、地球のどこへでも到達できる無限の航続距離を目指した、
冷戦時代の壮大な挑戦でした。
しかし、その翼が空を覆う日は訪れませんでした。
この記事では、この未完のプロジェクトの物語を紐解いていきます。
原子力飛行機計画とは?(概要・背景)
まるで神話の巨鳥のように、空に君臨し続ける存在を夢想した時代がありました。
原子力飛行機計画は、そんなSFのような構想を国家の威信をかけて実現しようとした、
20世紀半ばの巨大プロジェクトです。
いつ・誰が・どこで・何を目指したのか
この計画は、主に1940年代後半から1960年代初頭にかけて、
アメリカとソビエト連邦という二つの超大国によって推進されました。
アメリカでは空軍と原子力委員会(AEC)が主導し、
オークリッジ国立研究所(ORNL)やアイダホの国立原子炉試験場(当時NRTS、現INL)などで研究が進められました。
目指したのは、核兵器を搭載し、給油なしで長時間(連続数日規模)にわたって
敵国上空付近で待機し得る戦略爆撃機です。
これは、常時の報復能力=第二撃能力を確保するための抑止力強化策でした。
※用語注
第二撃能力:相手の先制核攻撃を受けても生き残った戦力で確実に反撃できる能力。
なぜ立ち上がったのか(当時の状況)
背景には、第二次世界大戦後に激化した米ソ冷戦があります。
当時のジェット爆撃機は航続距離が短く、
海外基地や空中給油への依存が高いという戦略的弱点がありました。
そんな中、たとえ基地が奇襲で無力化されたとしても、
機上で長時間待機できる「空中の抑止力」があれば反撃能力を維持できる。
そう考えられ、原子力推進の可能性が真剣に追求されたのです。
原子力飛行機計画の技術と仕組み
エンジンの心臓部で燃え盛るのは、化石燃料ではなく制御された原子の火。
この前代未聞の発想を実現するため、技術者たちは未知の領域へ踏み込みました。
中核となる技術要素
中核は小型原子炉を熱源として用いるジェット推進です。
通常のジェットは燃料の燃焼熱でタービンに仕事を与えるのに対し、
原子力案では原子炉の高温で吸入空気を加熱・膨張させて推力を得る設計でした。
理論上は燃料補給なしで、乗員交代や整備が許す限り飛行し続けられます。
※注:この方式は空気サイクルと総称され、原子炉の熱を直接空気に与える直接サイクルと、
ナトリウムなどの熱媒体を介して与える間接サイクルが研究されました。
どのように実現しようとしたか
アメリカはNEPA(Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft, 1946)で予備調査を開始し、
1951年にANP(Aircraft Nuclear Propulsion)計画へ移行。
本格的なエンジン・原子炉・遮蔽の開発に入りました。
ORNLではAircraft Reactor Experiment(ARE, 1954)で高温溶融塩炉の実証を実施。
アイダホの試験場ではGEがHTRE-1/2/3と呼ばれる原子炉直結ターボジェット実験を行い、
HTRE‑3で最大約35MW級の熱出力により、
J47改造エンジン2基を通算64時間連続運転するデータを得ています。
一方、飛行実験では、
B‑36爆撃機を改造したNB‑36H “The Crusader”に運用原子炉(推進には未使用)を積み、
1955年〜1957年にかけて47回・総215時間の飛行を実施。
目的は飛行中の原子炉挙動と遮蔽(シールド)性能の評価でした。
乗員区画は鉛とゴムで約12トン規模の遮蔽を施し、窓は厚い鉛ガラスに交換。
原子炉モジュールは地上管理のため着脱式でした。
ソ連でもTu‑95を改造したTu‑95LALで、
原子炉搭載飛行による遮蔽検証が行われました(推進には未使用)。
実は飛行実施時期の細部は資料間で差異があるのですが、
1961年前後に開始したのは確かのようです。
(※ロシア側一次資料は未確認)。
計画の実測・要件
- 地上原子炉ジェット実験:HTRE‑3が最大約35MWで64時間連続運転(J47改造2基)
- 飛行実験(米):NB‑36Hが1955–1957年に47回・計215時間、うち多数で原子炉を臨界運転
- 遮蔽重量(乗員区画):約12トンの鉛・ゴム遮蔽+水タンク等の補助遮蔽
- 設計要件(晩期の目標例):巡航M0.8–0.9/高度約35,000ft(約1.1万m)、
核エンジン耐久1,000時間級を志向
※用語注
HTRE:Heat Transfer Reactor Experiment(GEの原子炉直結ジェット実験)。
遮蔽(しゃへい):放射線が人や機器に届く強さを材料で弱めること。
放射能を消すわけではなく、外へ出る線を減らす「バリア」。
原子力飛行機なぜ未完に終わったのか
しあまりにも重い現実を背負っていました。
輝かしい未来像とは裏腹に、技術と安全、
そして時代の変化という名の巨大な壁が立ちはだかったのです。
技術的・安全上の課題
最大の壁は原子炉と遮蔽の重量でした。
航空機では重量増はそのまま航続・搭載量(ペイロード)の致命的低下につながります。
NB‑36Hの評価でも、乗員区画だけで約12トンの遮蔽が必要とされ、
さらに機体内の水タンク等で補助遮蔽を行いました。
加えて、墜落時の放射性物質拡散リスク、整備・乗員の被ばく管理といった
運用安全性のハードルが最後まで残りました。
政治的・経済的・社会的要因
1950年代後半には大陸間弾道ミサイル(ICBM)が実用段階に入りました。
これをきっかけに、「空に長時間滞空する爆撃機」よりも、
発射後短時間で到達するミサイルが戦略の主役になっていきます。
また、コストに対する効果も疑問視され始めました。
そしてついに、1961年3月、ケネディ大統領が開発の中止を議会に通告します。
原子炉+エンジン+機体の開発は停止され、
関連する高温材料・高性能炉などの基礎研究はAEC(原子力委員会)側で継続される方針に改められました。
原子力飛行機がもし実現していたら
歴史の「もしも」の扉を開けば、そこには原子力飛行機が空を舞う、
もう一つの「現在」があったかもしれません。
当時描かれていた未来像
軍事面においては、上空に指揮所を置いて常に部隊をコントロールできたり、
昼夜を問わず広い範囲を偵察・監視できるようになったかもしれません。
これによって、地上基地が攻撃されやすいという弱点をカバーできる可能性がありました。
民生転用としては、世界主要都市を無着陸で結ぶ超長距離旅客機・貨物機が構想されていました。
大量輸送が一度に可能になれば、
世界の物流や人の流れは今とは違うものとなっていたかもしれません。
現代からの展望と課題
現代の視点では、利便性に加えて廃炉・廃棄(使用済み炉の処理)、
核セキュリティ、環境影響など、当時想定が浅かった論点が立ちはだかります。
(日本の原発問題が一向に解決しないことからもわかりますね)
他方で、高温炉・耐放射線材料・溶融塩技術などの知見は、
のちの宇宙推進(例:原子力ロケット計画)や材料科学に間接的に資する面もありました。
(※評価に幅はありますが)。
ものすごく現実的に考えると、「現代」は実に悪夢の世界だったかもしれない
もし実用化して今も飛んでいたら、米ソ冷戦の「核のにらみ合い」は今以上に広がり、
空中衝突や事故のリスクまで戦略に組み込まれたでしょう。
また、環境被害は実に酷いことになっていたかもしれません。
実戦だけではなく、テスト中の墜落事故が繰り返されれば、
チェルノブイリ級の惨事が「飛行中の事故」として
各地にばらまかれる可能性がありました。
核の恐怖をさらに強め、事故や誤算で世界がもっと不安定になっていた可能性が高いでしょう。
こうしてみると、ICBMや潜水艦の方が「マシな悪夢」で、
原子力飛行機は「採用されなかった幸運の歴史」と言えるかもしれませんね。
年表(Timeline)
| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 1946年 | アメリカでNEPA(Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft)開始。 ORNL等で原子力航空推進の基礎調査。 |
| 1951年 | NEPAからANPへ再編(Aircraft Nuclear Propulsion)。 GE・P&W・ORNL等が本格開発に着手。 |
| 1952年9月 | 米空軍、B‑36をX‑6試験用に2機あてる方針を確認し、 コンベアに改修を割当(地上試験機/飛行試験機の計画)。 |
| 1954年 | ORNLでAircraft Reactor Experiment(ARE)の運転実証(高温溶融塩炉)。 アイダホではGEがHTRE計画を進展。 |
| 1955年9月 | NB‑36Hが原子炉(推進非使用)を搭載して初飛行。 以後1957年まで飛行試験を継続(47回)。 |
| 1957年10月 | ソ連がスプートニク1号打上げ。ICBM脅威が現実化。 |
| 1958年 | HTRE‑3で約35MW・64時間連続の「原子炉直結ジェット」地上運転を達成。 |
| 1961年 | ケネディ大統領が開発中止を通告。 原子力航空推進の実用化開発は停止、基礎研究へ集約。 ソ連側のTu‑95LALも同時期に縮小・中止の流れ。 |
FAQ
原子力飛行機計画はいつ始まった?
アメリカでは1946年のNEPAが源流です。
1951年にANPへ再編され、原子炉・エンジン・遮蔽の本格研究が始まりました。
飛行実験はNB‑36H(1955–57年)で遮蔽評価が実施されました。
なぜ中止されたの?
重量(炉+遮蔽)による性能限界と墜落時の汚染リスクに加え、
ICBMの台頭で戦略的価値が薄れたためです。
そして、1961年に大統領メッセージで開発中止がついに示されました。
現在も研究は続いている?
実用機の研究開発は1960年代に中止されています。
ただし当時の高温炉・材料・溶融塩技術などは、
宇宙推進や先端材料といった分野で研究継続・応用されています。
まとめ
- 結論: 原子力飛行機は、冷戦下に米ソが追求した
「理論上、給油不要の長時間滞空」を狙う戦略爆撃機構想だった。 - 根拠:溶融塩炉や原子炉直結ジェット(HTRE)などの地上実験、
NB‑36Hの飛行による遮蔽評価で要素検証は進んだ。 - 未完理由: 炉+遮蔽の重量/安全性の壁とICBM台頭により、1961年に開発中止となった。
- 未来インパクト:実現していれば物流・軍事の様相を変え得たが、
廃炉・核セキュリティ・環境の課題は現代基準で考えても大きい。
原子力飛行機計画は、技術への自信と時代の要請が生んだ、壮大でありながら危うい夢でした。
人類は原子の力で空を支配しようとしたものの、
その翼は重量とリスクに耐えきれず、離陸前に畳まれました。
もし空を舞っていたなら。
私たちの世界はどう変わっていたでしょうか。
…おそらく、地球上で「住める」場所が限りなく狭くなっていたのではないでしょうか。
そして私たちは常に怯えて暮らしていたことでしょう。
少なくとも、「民生転用で〜」という明るくて甘い未来は訪れていないと思われます。
参考資料・出典(一次情報・公的資料)
- ORNL(オークリッジ国立研究所):Aircraft Reactor Experiment (ARE)(1954, 概説・写真)
溶融塩炉の実運転実証(高温・短期間)。- 出典:Oak Ridge National Laboratory, “Aircraft Reactor Experiment (ARE),” ORNL History Exhibit(公式サイト)
- 米空軍(AFMC/DoD):History in Two: Manned Nuclear Aircraft Program(2021)
NEPA→ANPの経緯、HTRE‑3:最大約35MW・64時間、**設計要件(M0.8–0.9/35,000ft/耐久1000h)等。- 出典:U.S. Air Force Materiel Command History Office(公式解説)
- 米大統領文書(UCSB Presidency Project):Special Message to the Congress on the Defense Budget(1961‑3‑28)
原子力航空推進の開発停止方針(原子炉+エンジン+機体の開発を終了、関連の基礎研究はAECへ)。- 出典:American Presidency Project(公式アーカイブ)
- スミソニアン(Air & Space / National Air and Space Museum):NB‑36H関連ページ(写真・解説)
NB‑36Hの47回・215時間等の事実関係。- 出典:Smithsonian National Air and Space Museum(公的博物館)
- 米空軍(Kirtland AFB):This Week in History: Nuclear-powered aircraft program begins(2012)
NB‑36H:1955–1957年、47回・215時間(うち原子炉運転89時間)。- 出典:U.S. Air Force(公式サイト)
- ブルッキングス研究所:Converted B‑36 bomber (NB‑36H)
乗員区画の遮蔽約12トン、原子炉は数MW級(資料差異あり)、試験概要。- 出典:Brookings Institution(公共政策研究機関)