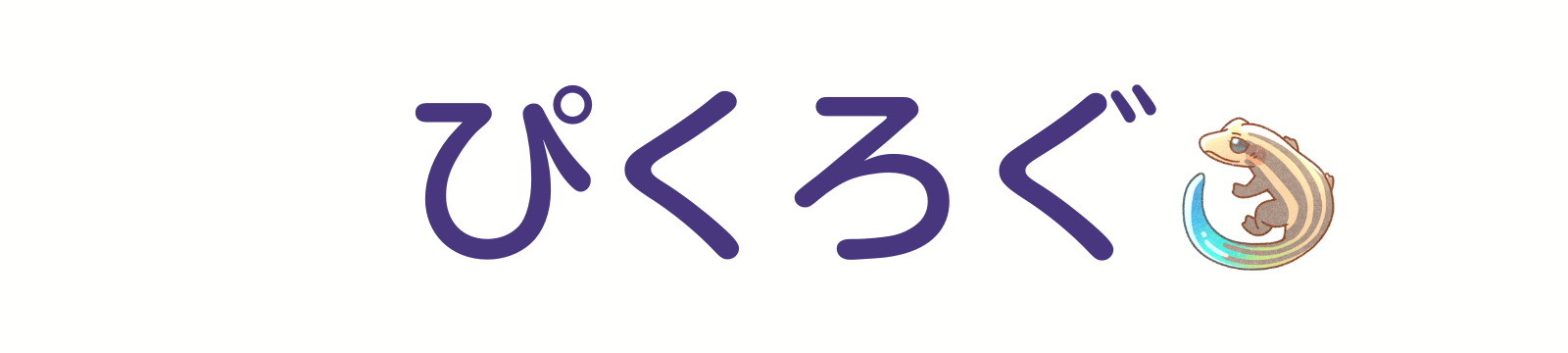オリオン計画。
耳にしたことはあるでしょうか?
オリオン計画というのは、
- 宇宙船の後方で小型の核爆発を連続的に起こし、
- その衝撃をプッシャープレートとショックアブソーバで受け止め、
- それを推力に変える核パルス推進の実用化を目指した、
- 1958〜60年代の米国プロジェクト
のことです。
最終的には条約と世論によって頓挫しましたが、
発想はダイダロス計画やスターライト計画へ受け継がれています。
ここでは、そんなオリオン計画について、簡単に掘り下げてみます。
内容柄どうしても専門用語が多くなっていますが、記事の後半に「用語解説」も設けていますので、ぜひ。
※専門用語を平易な言葉に置き換えて書く…というのがどうしても難しかったのです、ごめんなさい。
NASAの「オリオン宇宙船(Orion)」=アルテミス計画の有人カプセルとは別物です。
本記事の「オリオン計画」は核パルス推進の歴史的プロジェクトを指します。
オリオン計画とは?
改めて。
オリオン計画とは、核パルス推進による宇宙船の研究計画(1958–1960年代)のことです。
具体的な中身は以下の通り。
わかりやすいようにリスト化しています。上から順番に行われるイメージです。
- 宇宙船の後方で小型の核爆発を連続的に起こし、
- その衝撃をプッシャープレートと二段式ショックアブソーバで受け止め、
- 推力に変える核パルス推進の実用化を目指した研究計画
のこと。
1958年にジェネラル・アトミクス社で始まり、
テッド・テイラーやフリーマン・ダイソンらが中心となって検討が進みました。
最盛期には米空軍・ARPA・NASAも関与しましたが、1960年代半ばに中止されました。
核パルス推進とは?
核パルス推進とは、
- 宇宙船の外側で小型の核爆発を起こし、
- その衝撃(プラズマ噴流の運動量)をプッシャープレートで受け、
- 二段式ショックアブソーバでならして推力へ変換する方式
のことです。
部品の損耗等の課題はありましたが、設計の見直しで抑え込める目処も立っていました。
核パルス推進では、パルスユニット(成形炸薬で噴流を方向付けた小型核爆弾)を一定間隔で起爆し、
各パルスの蹴りを積み重ねて加速します。
外部式の比推力(Isp)は概ね3,000〜10,000秒が現実域と評価され、
設計や磁気遮蔽の工夫次第で10^5秒級の理論域も語られました。
化学ロケット(最大で約450秒)とは桁違いの世界であるため、高推力と高比推力の両立が視野に入ります。
歴史的にはウラムとエベレットの提案を起点に、
テイラーとダイソンがパルスユニットとプレート表面処理を洗練させました。
非核の模型試験も行われ、段階起爆で低高度飛行を確認した記録が残っています。
プレートのアブレーション(損耗)やショック機構の疲労といった課題はありましたが、
設計で抑え込める見込みが示されていました。
オリオン計画はどんな未来を描いていたのか?
彼らはどんな未来を描いていたのでしょうか?
それを一言でいうならば「宇宙輸送が海運並みのスケールになる」、そんな未来でした。
この方式が実現すれば、
宇宙輸送から「重いから無理」という制約が大幅に軽くなると期待されていました。
そして、ロケットによる「細いストロー補給」をやめ、巨大で頑丈な船で人と物資をがっつり運ぶ時代にする。
そういう未来を一気に引き寄せようとしていたのです。
これらを、さらに掘り下げてみます。
- まずは実用的な太陽系内輸送網
-
月面輸送・月面ロジスティクスの定期便、
そして火星・金星・木星への有人高速探査(fast-transit)。NASA向けの正式スタディでは、
1975〜1995年に主要な惑星ミッション能力に到達する開発ロードマップまで描いています。 - 「巨大・頑丈・広い・安い」宇宙船
-
高推力(押し出す力)と高比推力(燃費)を同時に満たす核パルスなら、
数千トン級の有効積載・150人規模の搭乗も現実的になるだろうと考えられていました。
軽量化地獄から解放し、海の船のような頑丈さで作る発想でした。ちなみに、当時の合言葉は「1965年までに火星、1970年までに土星」でした。
- 運用の現実路線
-
初期は地上発射案も検討しましたが、
のちに化学ロケットで軌道に上げてから核パルスを始動するモード(大気圏内の核爆発を避ける)を重視。運用・安全・整備、放射線環境、地上設備など、
運用面の課題洗い出しと解決策も設計目標に含められていました。 - さらに遠い未来への展望
-
フリーマン・ダイソンは、核融合パルスまで進めば恒星間輸送も射程に入ると試算していました。
経済成長が続くなら「約200年で星間航行が始まりうる」という長期の見通しを示していました。
(オリオン本体は星間用ではなく太陽系内志向)
なぜオリオン計画は実現しなかったのか?
夢のようなオリオン計画も、結局実現することがありませんでした。
それはなぜでしょうか?
結論から言うと、この計画を止める(頓挫させる)決定打となったのは、法と世論でした。
1963年、部分的核実験禁止条約(PTBT)が調印されたのです。
この条約は「大気圏・宇宙・水中でのいかなる核爆発」も禁ずるものです。
ゆえに、実地試験は不可能になりました。
さらに、1967年に発効された宇宙条約は大量破壊兵器の宇宙配備を禁止としました。
そうなると、当然パルスユニットを積む宇宙船は法的に極めて扱いにくくなってしまいます。
そこに、放射性降下物への社会的懸念、冷戦下の政治コスト、
そしてアポロ計画への予算集中が重なりました。
結果、技術的可能性の検証より前に政治的支持が失われたのです。
技術的な課題もたくさんあったのですが、
それでもこの「核爆発そのものを禁じる国際枠組み」が最大のボトルネックとなってしまったようです。
なお、技術面における難しい課題とは、
プレートの損耗、ショック吸収機構の耐久性、パルスユニットの安全・信頼性、
そして地上発射か軌道組立かといった運用上の論点など…
このように色々ありましたが、それでも「設計で対処可能」と見積もっていたのです。
(現実的な工学では、可能だと考えられていたとのことです)
受け継がれた種、夢は未来へ
このオリオン計画は完全に潰えてしまったのでしょうか?
いいえ。
アイデアそのものは、形を変えて生き続けています。
1970年代のダイダロス計画は、
慣性閉じ込め核融合のマイクロ爆発を連続させる無人恒星間探査機で、
光速の約12%、約50年で近傍恒星にフライバイする設計を検討しました。
そう、脈動で推すという思想は、オリオンの直系と言えます。
また、21世紀には、UCSBのProject Starlight/DEEP-INやBreakthrough Starshotが、
地上レーザーで光の帆を押す指向性エネルギー推進のロードマップを示しました。
グラム級探査機を0.1–0.2cにまで加速して近傍恒星へ送るという別解は、
重量という呪いを別の角度から解く発想で、オリオンと同じ地平に立っているといえるでしょう。
【補足】
NASAの「オリオン宇宙船」はSLSで打ち上げる有人カプセルで、核パルス推進とは無関係です。
アルテミスI(2022)は無人飛行で月周回を完了し、II・IIIでの有人計画が続いています。
用語解説
- 核パルス推進(核パルスエンジン)
-
宇宙船の外側で小型核爆発を連続起爆し、噴出プラズマの運動量で押す方式。
例えるならば。
ドラマーが太鼓を「ドン、ドン、ドン」と叩くたびに体が前へ押される感じ。
宇宙船の外で小さな核の花火を連続で鳴らし、
その衝撃で宇宙船を少しずつ前へ押し出していく方法。 - プッシャープレート
-
爆発衝撃を受け止める耐熱・耐衝撃の大板です。表面処理で損耗(アブレーション)を抑えます。
例えるならば、花火の衝撃を受け止める「鉄のキャッチャーミット」のような感じ。
とても頑丈で、表面は焦げや削れ(アブレーション)が最小ですむよう加工されている。 - 二段式ショックアブソーバ
-
衝撃を機械的に均し、船体に“なめらかな加速”を与える機構です。
例えるならば、車や自転車のサスペンションの豪華版。
爆発のドン!という瞬間的な押しを、
二段階のクッションで「ぐい〜っ」となめらかな加速に変えて、船内の人や機器を守る。 - パルスユニット
-
成形炸薬などで噴流方向を制御した小型核爆弾です。安全性・信頼性が要です。
例えるならば、進行方向に向けて「押しやすい風」を作る工夫をした、小型の核の花火。
形を整えた爆薬などで爆発の吹き出しができるだけ一方向(後ろ向き)になるようにし、
宇宙船を効率よく押す。 - 比推力(Isp)
-
燃料1kgあたりの速く投げる力を示す指標。
化学は〜450秒、核パルスは数千秒級(設計次第で10^5秒理論域)です。もっと噛み砕くならば、ロケットの燃費を表す数。
数が大きいほど、同じ燃料で遠く・速く行ける。
化学ロケットはおおむね「数百」の世界、
核パルスは「桁がひとつふたつ大きい」世界、
と覚えておけば十分。 - 原子力ロケット(核熱推進)との違い
-
核熱は炉内で推進剤を加熱・膨張させる連続式で、核パルスは脈動式。
例えるならば、ドライヤーの温風が「ずーっと出続ける」のが核熱(連続式)。
太鼓を「ドン、ドン、ドン」と叩くたびに前へ進むのが核パルス(脈動式)。
どちらも原子の力を使うが、出し方がまるで違う。 - ダイダロス計画
-
慣性閉じ込め核融合のマイクロ爆発で0.12cを狙う無人恒星間設計(1970年代)。
1970年代に考えられた無人の星間探査船の設計案。
噛み砕くと、
ちいさな核融合の花火を連続点火して、光の速さの約1割ちょっとまで機体を加速し、
別の星の近くを通り過ぎながら観測する構想のこと。 - スターライト計画(Project Starlight)
-
レーザー光帆で極小探査機を0.1–0.2c級へ加速する構想(現代)。
つまり、薄い帆(ほ)に地上の強力レーザーを当てて、
豆粒サイズの探査機を光の速さの1〜2割へ押し出してしまおう、
という現代のアイデア。
エンジンを積まず、光を風のように使う。 - アルテミス計画/オリオン宇宙船(NASA)
-
化学ロケット(SLS)で打ち上げる月探査の有人カプセルで、名称は同じでも本計画とは無関係。
こちらは月へ人を送る現行のプロジェクト。
「オリオン」という名前は同じでも、
化学ロケット(SLS)で打ち上げる「月探査用の有人カプセル」のこと。
核パルスのオリオン計画とは別物。
年表(主な流れ)
- 1955:ウラム&エベレットが外部核爆発推進を提案
- 1958:ジェネラル・アトミクスで「オリオン計画」が始動
- 1959:非核の模型試験で段階起爆・低高度飛行を確認
- 1963:部分的核実験禁止条約(PTBT)が発効し、大気圏・宇宙での核爆発が禁止
- 1964–65:政治的支持を喪失し、計画は凍結へ
- 1967:宇宙条約で大量破壊兵器の宇宙配備が禁止
- 1970年代:BIS「ダイダロス計画」が検討される
- 2010年代〜:UCSB「スターライト」/ Starshotなど指向性エネルギー推進が台頭
関連プロジェクト比較表
似たような計画(プロジェクト)が複数あるので、整理してみました。
| プロジェクト | 推進方式 | 代表的目標 | 有人/無人 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| オリオン計画 | 核パルス (外部核爆発) | 月・火星・外惑星 /恒星間案 | 有人想定 | 中止 |
| ダイダロス計画 | 核融合パルス | 0.12cで近傍恒星 (50年フライバイ) | 無人 | 研究設計 |
| スターライト/Starshot | レーザー光帆 | 0.1–0.2cで近傍恒星へ | 無人(極小機) | 研究開発 |
| NASA オリオン宇宙船 | 化学(SLS) | 月軌道・帰還 | 有人 | 運用計画中 |
FAQ
- オリオン計画は実現可能だった?
-
技術課題は多いが設計上は対処可能と見積もられていた。
止めたのは条約と世論。 - 「オリオン計画」と「オリオン宇宙船」(NASA)は同じ?
-
別物。
前者は核パルス推進の歴史的研究・計画、後者はアルテミス計画で月に人を送る有人カプセル。 - なぜ宇宙の推進力が「核」なのか?
-
宇宙旅行のキモは「燃料1キロでどれだけ速く投げられるか(比推力)」。
つまり、核はエネルギー密度が高く比推力が大きく、長距離・大質量輸送で優位なため。
核反応は化学反応の数百万倍のエネルギー密度を持ち、高比推力と大推力の両立の道を開ける。 - 日本でも「宇宙船」や「原子力ロケット」はの研究は進んでいる?
-
日本でも原子力の宇宙利用(核熱・核電推進など)の議論・基礎研究はあるが、
核パルス推進(原爆パルス)の実用化計画は存在しない。
国際条約と安全規制が大前提となるため。
※核爆発実験そのものが国際的にNG。日本ももちろん。
まとめ
この計画は、技術が足りなくて(技術面の壁にぶつかって)でできなかった、
のではなく、社会が止めた稀有なケースでした。
もしオリオン計画が成功していたなら。
月の基地は定番となり、火星は長期休暇の行き先になっていたかもしれませんね。
最後に…
未完であることは失敗と同義ではありません。
むしろ、倫理と法が追いつくまで保留された可能性だと言い換えられるかもしれません。
いえ、それ以上に「核爆発」ではない、別の方法を見つけ出し、
それこそ人類と地球の平和にできる方法を探すための道を与えられたとも言えるでしょう。
今の世界状況からすると、このオリオン計画はあのタイミングで中止になって良かったのかもしれません。
そう言うことを考えると、いろんなことが「ものすごく遠い未来」のように感じてしまいますが、
それでも、いつか叶う日はきっとくると願って。
出典・参考
- Nuclear Pulse Propulsion – Orion and Beyond(AIAA 2000)
- General Atomics, Nuclear Pulse Space Vehicle Study (GA-5009) Vol. III/IV(1964–66)
- Partial Test Ban Treaty(1963)条文・解説
- Outer Space Treaty(1967)条文(UNOOSA)
- I. A. Crawford, JBIS(2009)— ダイダロス計画レビュー
- UCSB Project Starlight / “A Roadmap to Interstellar Flight”(2016)
- NASA Orion(アルテミス計画の有人宇宙船)公式解説