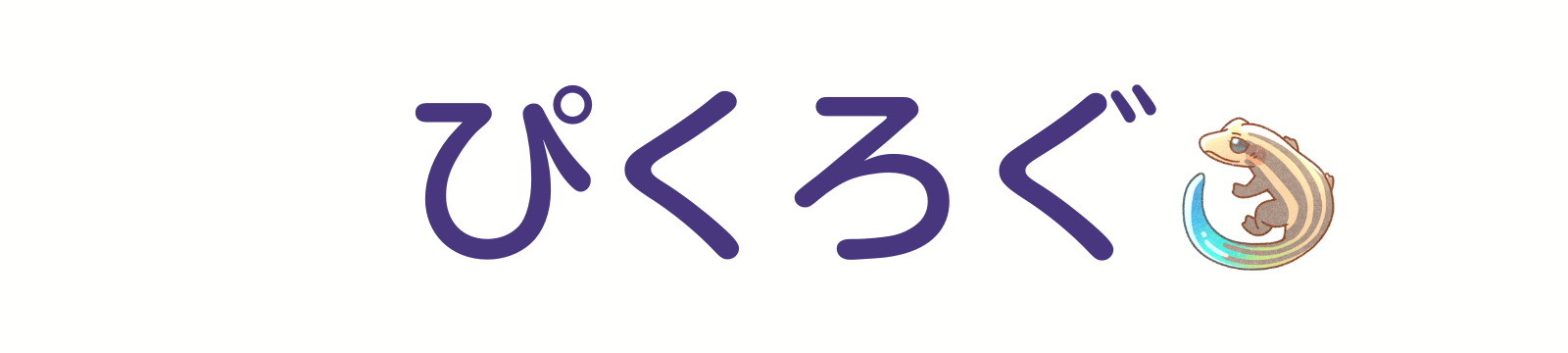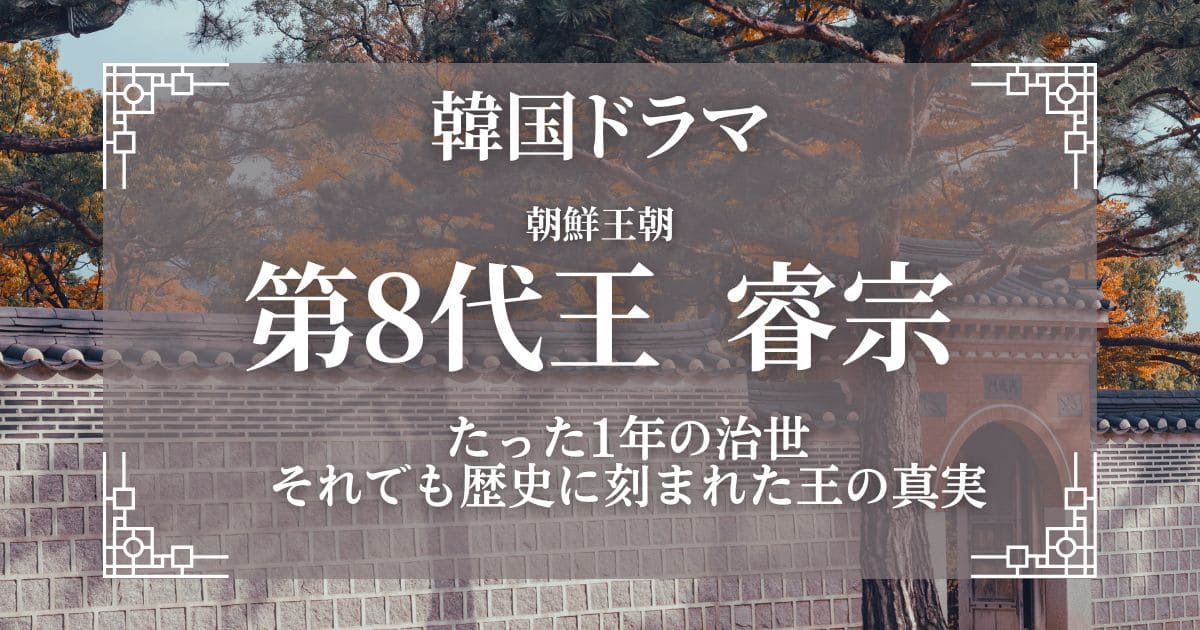今回ご紹介するのは、朝鮮王朝の第8代国王・睿宗(えいそう/イェジョン)。
ドラマでは影が薄い…かもしれませんが、それもそのはず、
わずか19歳でこの世を去り、在位期間もたった1年余りという異例の王なんですよね。
なので、ドラマでは脇役として描かれることが多い睿宗。
ちなみに、「恋慕」はこの時代が背景のようです。
※話自体は完全フィクションですが、王様が短命等は描かれています。
兄の急死、父・世祖の複雑な決断、王位継承をめぐる政治の駆け引き、
さらには短い治世の中でも起こった重大事件など…。
この記事では、そんな睿宗について、史実に基づいてQ&A形式でまとめています。
ぜひ最後まで読んでいただけたら嬉しいです♪
睿宗ってどんな人?韓国ドラマにも登場する若くして亡くなった王の正体は?
まずは基本的なことからおさえてみよう!
- 朝鮮王朝第8代の国王
- 生涯:1450年2月12日〜1469年12月31日(19歳)
- 治世:1468年9月7日〜1469年12月31日までの1年間
- 即位名:睿宗(えいそう・イェジョン)
睿宗はいつ生まれて、どんな家系の出身だった?
睿宗は、朝鮮王朝第7代王・世祖(セジョ)と貞熹王后 尹氏の間に生まれました。
生まれた場所は漢城府(現在のソウル)で、
王子として「海陽大君(ヘヤンデグン)」の称号を与えられています。。
なお、兄は早世した懿敬世子(いけいせいし、ウィギョンセジャ)です。
睿宗はなぜ王になったの?兄の死と世祖の決断とは?
前述の通り、睿宗には12歳年上の兄・懿敬世子がいました。
そんな懿敬世子は父・世祖が最も信頼する王位継承者でしたが、
1457年9月、わずか19歳の若さで病死してしまいます。
ですが、実は懿敬世子にはすでに息子が生まれており、年齢的にも王位を継ぐ可能性がありました。
しかし、父・世祖は、自身がかつて甥の端宗から王位を奪って即位した過去があったがゆえに、
孫に王位を譲ることで再び権力闘争が起こるのを強く恐れていました。
そのため、世祖は懿敬世子の子ではなく、弟にあたる睿宗を後継者に選びました。
こうして睿宗は、懿敬世子が亡くなった同年の1457年12月、
まだ7歳という若さで正式に王世子に冊立されることとなりました。
ちなみに、この時に懿敬世子の息子は、のちに第9代王となる成宗です。
睿宗はどれくらいの期間、王として在位したの?
睿宗は1468年9月7日に父・世祖の譲位を受けて即位したものの、1469年12月31日に亡くなりました。
そう、在位期間はわずか1年3か月ほどしかありません。
これは朝鮮王朝の王の中でも2番目に短い治世です。
※第12代王である仁宗(インジョン)治世は約8か月とされており、朝鮮王朝で最も短いです。
睿宗の時代に何があった?政治や事件、改革をわかりやすく解説
睿宗の在位期間はわずか1年余りと短かったものの、
その間に朝鮮王朝の政治体制に大きな影響を与える出来事がいくつもあります。
王権を巡る勢力争いや法典の編纂、
母である貞熹王后による政治代行など、
睿宗の時代は短命ながらも決して静かな時代ではなかったのです。
睿宗の治世中に起こった「南怡(ナミ)の謀反」とは?
睿宗の治世において最も大きな事件のひとつが、「南怡の獄」と呼ばれる粛清事件です。
南怡(ナミ)は、前王・世祖のもとで功績を挙げ、
特に「咸鏡道の乱」とも呼ばれる「李施愛の乱」を鎮圧したことで名を馳せた若き武臣でした。
ゆえに、世祖に厚遇され、若くして兵曹判書(現在で言う国防相)という高位に昇進していた人物です。
しかし、世祖の死後に即位した睿宗にとっては、
南怡の存在は次第に「脅威」と映るようになってしまいました。
当時、世祖の治世で台頭した古参功臣(旧功臣)と、
李施愛の乱の鎮圧後に登用された新たな功臣(新功臣)の間には、激しい勢力争いが起きていました。
南怡はまさにその新功臣の象徴的存在でしたが、
睿宗はこのバランスを是正しようとし、
旧功臣を重用する方針を打ち出したとされています。
その最中、南怡が謀反を企てたとの密告が寄せられます。
この密告を行ったのは、政治的ライバル関係にあったユ・ジャグァン。
南怡の詩文の一節が「国を得ることができなければ(미득국/未得國)」と解釈され、
謀反の意志をにじませたと告発したのです。
そして、南怡は拷問の末に罪を認めさせられ、処刑されました。
ですが、実はこの解釈には後世まで疑問がつきまとっています。
この事件は、若き王・睿宗が旧功臣と新功臣の間に揺れ動きながらも、
統治体制の再編を試みた結果として捉えることができます。
彼の政治的意志を示した一方で、多くの論争を残す決断でもあったとも言えるでしょう。
睿宗の治世は母・貞熹王后の「垂簾聴政」だったって本当?
睿宗が即位したのは1468年、当時19歳でしたが、
生来の体の弱さから王としての政務遂行が危ぶまれていました。
そこで実母である貞熹王后(チョンヒワンフ)が
政務を代行する「垂簾聴政(すいれんちょうせい)」が始まります。
これは、王の背後に帳(すだれ)を垂らし、
その向こうで王に代わって母后が政治を執るという形式で、
事実上の摂政制度です。
この貞熹王后による垂簾聴政は、朝鮮王朝史上初めての試みであり、
のちの成宗や中宗の時代にも継承されていく政治制度の先駆けとなりました。
貞熹王后は夫・世祖の強権政治を支えていた中心人物であり、
政務にも明るかったため、睿宗の短い治世を安定的に支えました。
そんな貞熹王后の影響力は非常に強かったため、
若き睿宗の自主性がどの程度発揮されたのかについては、歴史家の間でも意見が分かれています。
睿宗が自ら決断したとされる事柄もいくつか存在していますが、
王としての実権は限られていたと見る向きもあります。
いずれにしても、睿宗の治世は母の助けなくしては語れず、
「母后が治めた治世」として歴史に記録されているというのが実情のようです。
睿宗と「経国大典」の完成、その意義とは?
朝鮮王朝の基本法典である「経国大典」は、
国家の根幹を定める重要な法典として知られています。
その編纂は父・世祖の時代に始まりましたが、
最終的に完成したのは、実は睿宗の治世中の1469年でした。
完成した法典は、その年の干支から「己丑大典」とも呼ばれています。
しかしながら、睿宗はこの法典の正式な公布を見届けることなく、
同年のうちに急逝してしまいました。
そのため「経国大典」の頒布および施行は、
後を継いだ成宗の代に行われています。
法制度の基盤となる法典に関して、
睿宗が主体的に関与した(編纂に口出しした等)という情報はありませんが、
睿宗の時代に完成したことは確かなようです。
睿宗の家族構成は?子どもや后妃について
睿宗の正室・継室はどんな人物だった?
睿宗の最初の正室は、功臣・韓明澮の娘である章順王后 韓氏です。
彼女は王世子時代に結婚し、男子(仁城大君)をもうけましたが、出産後に病死してしまいます。
のちに、側室だった安順王后 韓氏(韓伯倫の娘)が正室となり、複数の子女を産みました。
※いずれも「韓氏」ですが、別の家系出身です。
睿宗には子どもがいたの?なぜ息子ではなく甥が王位を継いだ?
睿宗には仁城大君、斉安大君、もう1人の王子がいましたが、
いずれも幼く、王位継承には不適とされました。
結局、貞熹王后と重臣・韓明澮らの政治的判断によって、
兄・懿敬世子の子である成宗が次の王に即位しました。
睿宗の兄・義敬世子や甥・成宗との関係は?
兄の義敬世子 李暲(イ・ジャン)は睿宗より12歳年上で、早世していた。義敬世子の息子が後の成宗であり、睿宗の甥にあたる。睿宗と成宗の関係は親族関係以上に政治的な意味合いも持ち、睿宗が亡くなると、成宗が跡を継いだ。
睿宗の死因は?19歳で亡くなった理由と死の謎
睿宗は生まれつき病弱であり、長年「足の病(俗に言う“足癬”)」に苦しんでいたとされています。
死因は「壊死性の皮膚感染症(連続組織炎)」からの敗血症と推測されており、
突然の死というよりは持病の悪化によるものであるようです。
睿宗の評価はどうだった?歴史上の位置づけを探る
睿宗は名君?凡庸な王?後世の評価とは?
睿宗の治世は短かったため、政治的な実績は限定的ですが、
南怡の処断や経国大典の編纂完成やなどを見ると、自らの信念と判断を持って政治に臨んだ一面が評価されています。
総じて凡庸とも名君とも断定しがたいが、強い意志を持った王ではあったようです。
父・世祖や甥・成宗と比べて、睿宗の政治力はどうだった?
父・世祖はクーデターで王位を獲得し、強権政治を行った人物です。
一方、甥・成宗は長期政権で安定をもたらした名君とされています。
それに比べ、睿宗は治世が短く、また垂簾聴政により実権も限定的でした。
ですが、自身の立場を理解しつつも意思を示す場面は多く、政治的力量を見せた王とも言えるようです。
睿宗の短命がもたらした王位継承の影響とは?
睿宗の早世は王位継承に大きな混乱をもたらす可能性がありましたが、
貞熹王后や韓明澮らの調整により、成宗への円滑な継承が実現しました。
結果的に王室の安定が保たれました。
あとがき
この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
短命ながらも朝鮮王朝の歴史に確かな足跡を残した睿宗。
彼の人生には、王族としての葛藤、政治の重圧、そして静かに訪れた死がありました。
兄の死を経て王世子となり、母・貞熹王后のもとで王位に就いた彼の姿には、
表舞台に立つことの宿命と儚さが映し出されている…かもしれませんね。